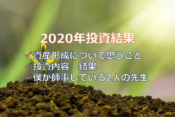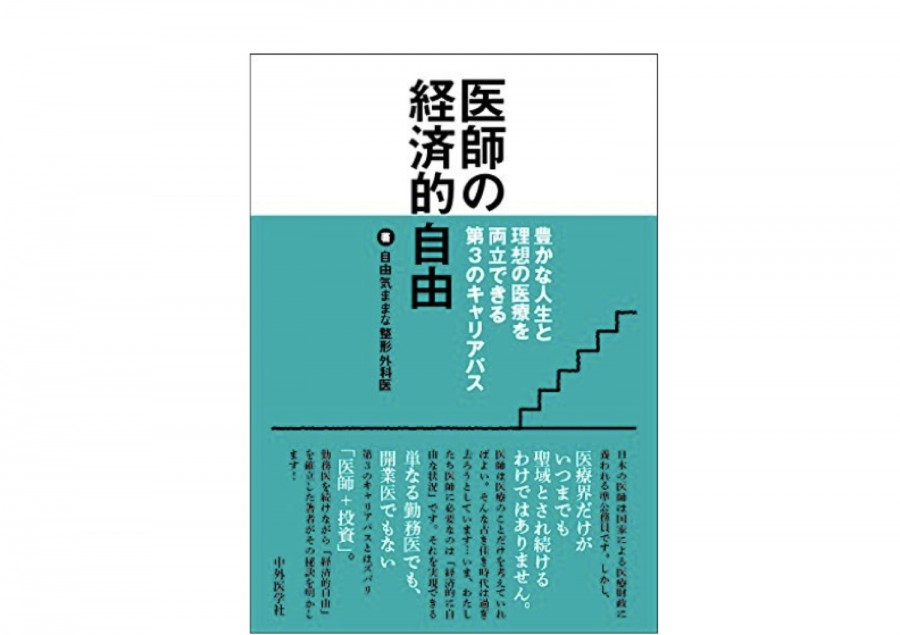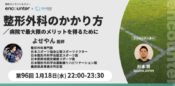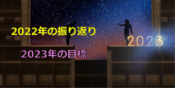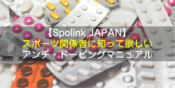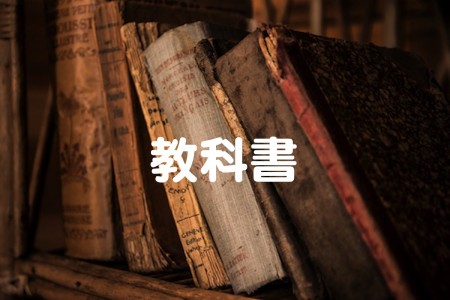iDeCo(個人型確定拠出年金)を活用しよう|メリット・デメリットを知った上で賢く運用していこう!

どうも、こんにちは。
若手整形外科医のよせやんです。
 よせやん
よせやん
今日は社会人フットサル都道府県リーグの試合がありました。
1得点決めたけど試合には負けてしまいました。
気持ちを切り替えて来週に備えます。
さて、今日は日曜日なので資産形成についての記事です。
前回に引き続き、iDeCo(個人型確定拠出年金)についてお話しします。
しかし、iDeCoの話をすると「それって投資でしょう?怖いから自分はやらない!」って言う方もいますが、そういう方は制度を理解していない方がほとんどなのではないでしょうか。
特にある程度収入のある方にとってはiDeCoはやらない理由が見つからないような制度ですが、制度について理解してメリットとデメリットを知った上で、自分で判断すべきでしょう。
 よせやん
よせやん
というわけで、今回はiDeCoの活用方法についてお話ししていきます。
法人を持っている方であれば小規模企業共済やセーフティ共済でも節税ができますが、法人を持っていない人にとっては貴重な節税手段の1つになるので、是非とも知っておいた方がいいでしょう。
Contents
若手医師の資産形成
まず、若手医師の僕がやっている資産形成を紹介します。
- 資産形成の勉強
- 家計簿
- 銀行の選択
- クレジットカードの選択
- ふるさと納税
- 給料天引き
- iDeCo
- つみたてNISA
- 外貨積立
- 海外ETF
- 投資信託
- 楽天ポイント投資
- 健康投資
など
基本は誰にでもできることばかりです。
今後は仕事に支障をきたさない範囲でスモールビジネスや不動産なども始めていく予定です。
今回は、この中でも前回に引き続きiDeCo(個人型確定拠出年金)についてお話ししていきます。
資産形成を行う上での再現性には個人差があり、必ずしも利益が出るとは限りません。当ブログを参考にして行ったことで損益が出ても責任は負いかねますので、資産形成は自己責任にて行って頂くようお願いします。
iDeCoのメリット
前回、iDeCoとはどんなものなのかお話ししました。
iDeCoのメリットを再度まとめておきます。
- 掛金が全額所得控除
- 分配金などの運用利益が非課税
- 受取方法に関わらず一定額まで非課税
まず、掛金が全額所得控除となります。
節税額は、年収や掛金に応じて変動しますが、積み立てる全期間に適用されるので60歳までの期間を考えるとかなり大きな額を節税できることになります。
また、投資信託などの金融商品で運用する場合、通常だと20.315%の税金がかかりますが、iDeCoの場合には運用益がすべて非課税になります。
そして受取に関しても、年金で受け取る場合は「公的年金控除」、一時金で受け取る場合は「退職所得控除」が適用されます。
例えば、一時金受取場合の退職所得控除額は800万円 + 70万円 ×(勤続年数 - 20年)となっています。
実際にどれくらいの控除が得られるか知りたい方は下のシミュレーションをしてみて下さい。
僕の場合ですと、1年間で節税できる金額は35-40万円、60歳の受け取りまでに節税できる金額は1,000万円くらいになります。
基本的に所得が多く、所得税・住民税が多い方ほどより節税が可能です。
ですので、医師など高所得者であれば基本的に使わなくては損な制度だと思います。
 よせやん
よせやん
iDeCoのデメリット
続いて、一応iDeCoのデメリットについても紹介しておきます。
- 原則60歳まで引き出すことができない
- 投資で利益が出るかは不確定
- 対象となる商品が少ない
iDeCoでは、原則60歳にならないと資金を引き出すことができません。
もしも将来手元の資金が枯渇したとしても、iDeCoを解約して現金化することができないのです。
このようにiDeCoには流動性はありませんので、生活資金ではなく絶対に使わない余剰資金で運用しましょう。
ですので、子供の教育資金や住宅ローンなど将来の資金計画をしっかり考えておく必要があるでしょう。
ただ、iDeCoの掛金なんて限度額が月額12,000円〜68,000円なので、医師の方でよっぽどお金を散財する方でなければ全く問題にならないと思います。
個人的には全くデメリットと思っていません。
次に、これは当然といえば当然なのですが、投資で利益が出るかどうかは不確定です。
投資信託、信託商品での運用を選択した場合は、当然のことながら運用でマイナスとなることもないとは限りません。
特にアクティブファンドを選択した場合は変動が激しくなります。
個人的には信託報酬が安く、安定しているインデックスファンドで積み立てていくのが一番無難だとは思います。
iDeCoの話をすると、「投資は怖いからやらない!」と言ってくる人とがいますが、そういう人は定期預金や保険などの元本確保型の商品を選択して下さい。
運用に回したお金(元本)が減ることは原則ありません。
ただし、iDeCo向けの定期預金の利率は0.02%、ある積立年金保険の利率は0.005%と非常に低い利率になっていますので、資産を増やすという意味ではあまり意味を果たさないとは思っておいた方がいいでしょう。
また、一般的にはiDeCoは対象となる商品が少ないと言われますが、個人的には全くそうは思いません。
むしろ特に今まで資産形成を行ってこなかったら人からすると商品が多くてどれを選んだらわからないくらいではないでしょうか。
若手医師の僕の運用方法

最後に若手医師である僕の運用方法を紹介しておきます。
僕の場合は、第1号被保険者に該当するので、掛金はMAXの月額68,000円に設定しています。
運用商品としては、インデックスファンドである楽天VTI(楽天・全米株式インデックスファンド)を選択しています。
僕は海外ETFでVT、VTI、VGTなどに投資しているのでその流れでですね。
さすがにまだ将来の年金の受け取り方法までは考えていません。
上級者になってくると、定期預金で普段は積み立てておいて、株価暴落時に株式クラスへのスイッチングで集中投資することも可能ですが、あまり知識のない方はインデックスファンドで毎月積立をすれば自然とドルコスト平均法で運用することになるのでそちらをお勧めしますね。
おわりに
以上、今回はiDeCo(個人型確定拠出年金)の活用方法についてお話ししました。
今後さらに国民年金の支給額が減り、高所得者の負担が増えるであろうことがニュースとなっていますが、iDeCoを活用すれば節税をしながら投信積立で将来の退職金・年金を自分で用意することが可能です。
特に医師のようにある程度の所得があり、所得税率が30%以上あるような場合には節税効果が大きく、加入するだけで税金が安くなる仕組みは願ったりかなったりです。
節税効果を含めると長期的にみて損をする可能性はほぼないでしょう。
法人を持っている方であれば小規模企業共済やセーフティ共済でも節税ができますが、法人を持っていない人にとっては是非ともやっておくべき資産形成の1つだと思います。
 よせやん
よせやん
この記事で、制度について理解してメリットとデメリットを知った上で、賢く活用していきましょう。
本気でスポーツ医学と運動器診療を学びたい人のために!
- どこにいても(都会でも地方でも)
- 誰でも(医師・理学療法士・鍼灸師・柔道整復師・トレーナー・学生などスポーツに関わる全ての人)
- いつでも(24時間)
利用可能なスポーツセミナー動画配信サービス!!
1週間1円トライアル実施中!!