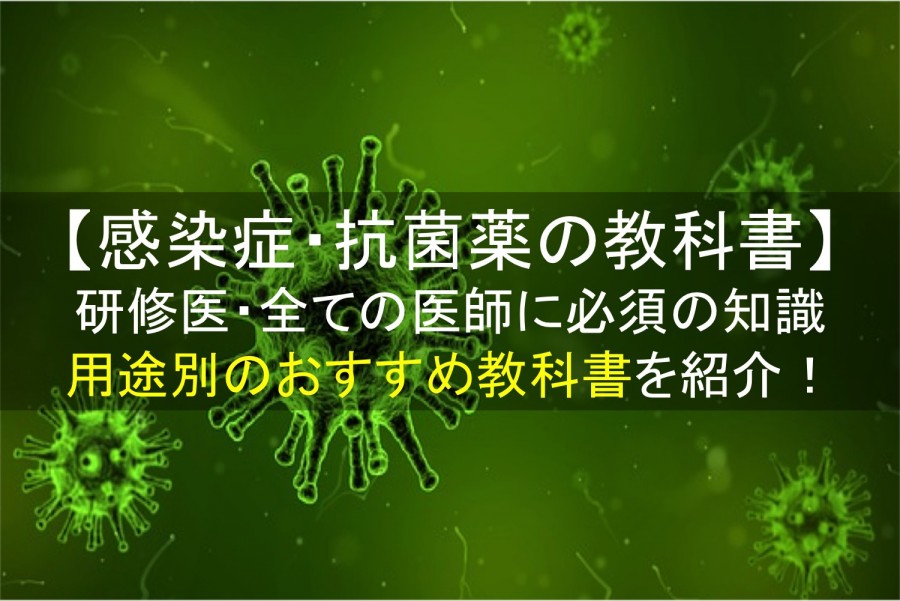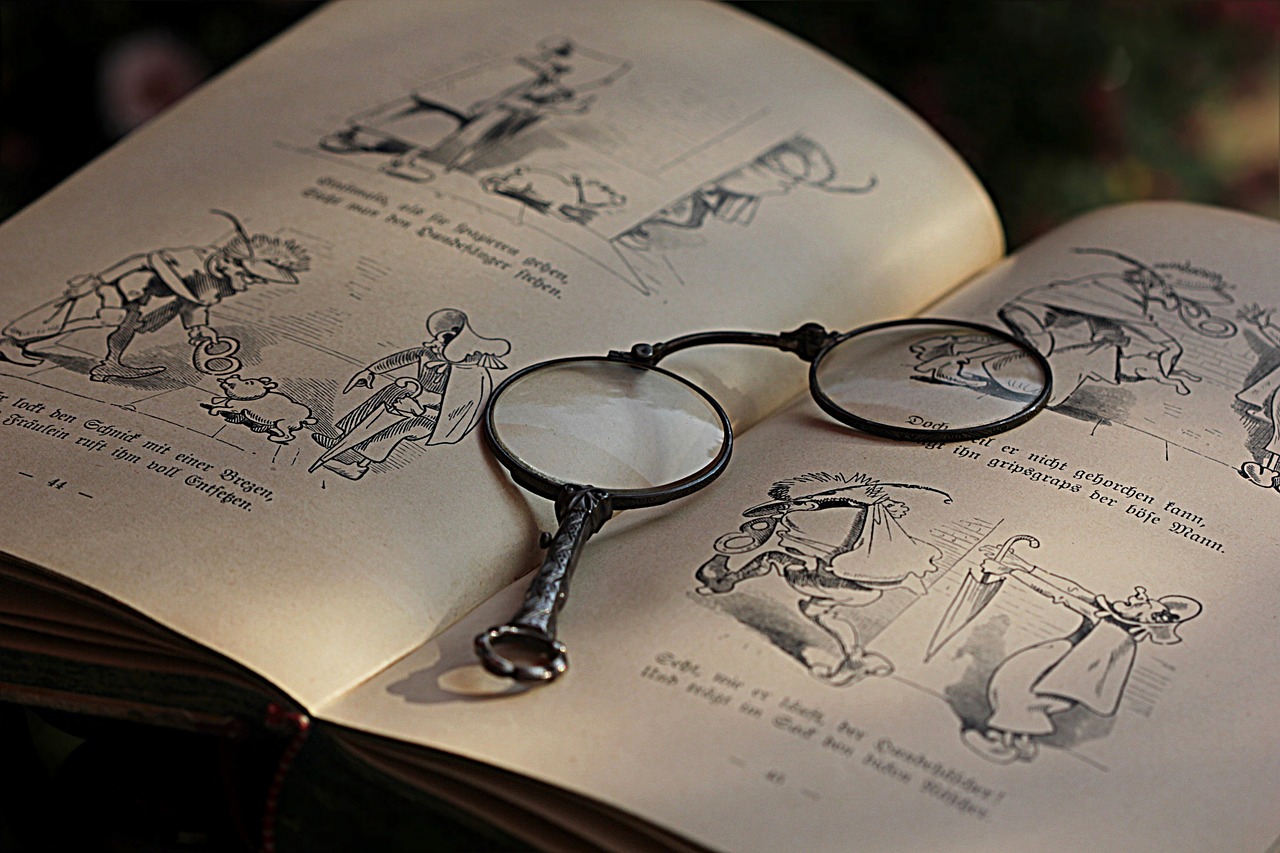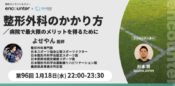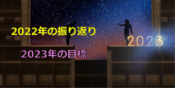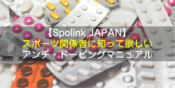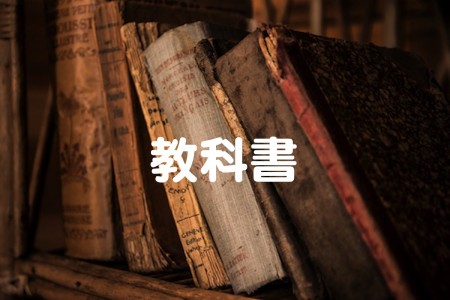整形外科での初期研修|初期研修医のローテートの仕方

どうも、こんにちは。
若手整形外科医のよせやんです。
昨日は埼玉まで行っていましたが、今日は戻ってきて仕事をしております。しかも、今日は大学当直です…。
さて、先日ちょっと触れましたが、今週の中頃、来年5月から赴任予定の病院の歓送迎会がありました。この病院は僕が初期研修医として2年間初期研修をした病院でもあります。そして、今年1年間の空いている火・金曜に関節鏡手術の勉強をさせてもらっていた病院でもあります。
歓送迎会に行ってちょっと懐かしい気持ちになりましたし、たまに読者の方から「研修医時代にどういう生活をしていましたか?」という質問を頂くことがあるので、今日は「自分の研修医時代、特に整形外科研修」を振り返ってみようと思います。
Contents
はじめに
医師の初期研修の期間は2年間あり、現在は、その間にいろいろな科を回って勉強していく、いわゆるスーパーローテート方式で初期研修を行います。
内科・救急科・地域医療の3科目が必修とされており、外科・麻酔科・小児科・産婦人科・精神科の中から2科目が選択必修となっています。ただし、詳しいプログラムは各研修病院によって異なります。
初期研修病院を決める前に、希望する病院の研修プログラムに関しては必ず確認しておきましょう。
自由に研修先を決めることができる期間がどれだけあるかは非常に大切です。
また、直接指導して頂く、近い年次の先生の存在が重要です。
研修医時代は、医師としての基盤を作り上げる期間になるので、しっかりと指導してくれる年次の近い先生がその病院にいるかどうか、そして、指導してくれる人ができる人かどうかというのは意外に大きなポイントになってきます。
僕の初期研修プログラム
僕の初期研修プログラムを紹介しておきます。

研修医1年目のときにその病院に勤務されていた4年目の整形外科医の先生がめちゃくちゃ優秀だったのですが、その先生は1年間しかその病院にいないことが決まっていました。
本来、病院で決められていたプログラムでは、1年目の10月〜3月の6ヶ月間は、内科で研修する予定になっていました。しかし、僕はなんとしてもその先生の下で整形外科の研修をしたかったので、研修委員長の先生、院長にお願いしに行き、1年目の1、2月に整形外科で研修できるように研修プログラムを変更して頂きました。
結局、整形外科では、2年間で計9ヶ月間研修させて頂きました。
自由選択可能な期間がこの9ヶ月間であったので、実際には救急で気胸の患者さんに対応するために胸部外科を回ろうかなとか、頭部外傷の患者さんに対応するために脳神経外科を回ろうかなと迷っていましたが、そういうことは当直などの救急対応で勉強しようと思い、結局すべてを整形外科での研修に当てました。
整形外科での研修
では、実際に整形外科研修でどのように生活していたかを紹介していきます。
研修医1年目
1年目の8月と1、2月に整形外科で研修させて頂きましたが、8月は初めての整形外科での研修でしたし、1ヶ月間しかなかったので、学生のときのようにほぼ見学といった感じでした。
基本的に手術室にいて、オペ手伝いをしていました。ただ、この期間に腕神経叢ブロック(伝達麻酔)と腰椎麻酔のやり方を覚えました。
1、2月の研修からは、より実践的な研修をさせて頂けるようになり、週1回水曜日に初診の外来を手伝い、水曜日と木曜日に徐々に増えていく再診の患者さんを診るための再診日にして頂きました。
その他の日中の時間は、主に手術の助手をしていて、救急が来ればその対応をしていました。この時期に腰椎麻酔も腕神経叢ブロックも自信を持ってできるようになりました。
そして、空き時間に入院患者さんの回診、薬や点滴のオーダー、手術のオーダー、消毒や抜糸・ギプス交換など、そして手術前のインフォームドコンセントをしていました。木曜の午後は手術がなかったので、昼過ぎに病棟に上がってきていましたが、その他の曜日はだいたい夕方、遅いと病棟に上がるのが21、22時になることもありました。
この時期には、初診外来や救急外来で担当した症例は自分が担当させてもらえる(難しくない手術症例なら執刀させてもらえる)ということになっていたので、初めて自分で執刀する手術を経験しました。
また、自分が救急当番でないときでも、4年目の尊敬する先輩が外科当直や整形外科待機の当番の日は必ず病院に残って張り付かせてもらっていました。ただの思いつきですが、自分の中でその先生より絶対に先に帰らないと決めていたので、帰る時間もいつも1時、2時とかになっていた気がします。
そして、このライフサイクルが今も染み付いたままになっています。「先生は病院が好きですね」、とか「他にやることないんですか?」と言われますが、もうこの生活が染み付いていて変えることは難しそうです。
この2ヶ月で、本当に整形外科医としての基盤が作り上げられた気がします。
研修医2年目
研修医2年目のときの整形外科研修は10〜3月の最後の6ヶ月間にしたので、それまでに研修医レポートなど研修医として終わらせておくべきことは全て終わらせていました。
1年目の整形外科研修で、ある程度、整形外科医としての基盤ができていたので、2年目の研修ではもう研修医としてではなく、1人のスタッフとして扱って頂いていた感じになっていました。
もちろんできないことはいっぱいありますので、その際にはいつも助けてもらっていましたけど。明確に外来日、手術日などを曜日ごとに整形外科の先生と同じように割り振ってもらい、基本的にはそれに従って行動していました。
この6ヶ月間で覚えたことは数えきれません。そして、続けて6か月間研修したことに非常に意味があったように思います。
手術した症例にしても、その後の経過を外来で半年間フォローしていたので、こうやって後療法(外固定やリハビリなど)していけばいいんだ!という流れを知ることができたのが大きかったと思いますし、連続して長くいることで必然的にやらせてもらえることも増えていきました。
結局2年目の半年間で、自分で執刀した手術症例は70例になっていました。名前だけ執刀医になっていて、ほとんどを上級医にやって頂いた難しい手術はカウントしていません。
上級医に「日本で1番手術した研修医なんじゃない?」と言われましたが、他の研修病院のことは知らないのでわかりませんが。病棟での担当患者さんも20〜30人くらい持っていたと思います。
そして、この期間にもう1人の尊敬する先生に出会いました。臨床能力もめちゃくちゃ高いのに、スポーツに関わる研究をいろいろとされている先生で、大学病院に転勤になった今でも、その先生には学会発表や論文に関してお世話になっています。
また、このときの繋がりで、サッカーのマッチドクターやメディカルチェックなどのスポーツドクターとしての仕事を回して頂いたり、スポーツ関連の学会や勉強会の情報を回して頂いたりして頂けるようになりました。
おわりに
「専門のことを勉強するのはその科に行ってからでいい」と言わることがあるかもしれませんが、
研修医時代をどう過ごしたかによって、医師3年目の整形外科医としてのスタートラインに立った時点での実力の差は天と地ほどの差ができていると思います。
整形外科医になったときに少しでもできる立場に立っていることは、当然それなりに利点があります。
その一つは、同期がわからないことがあったときに聞いてきてくれることでしょう。もちろん聞かれても自分も知らないことなんて腐るほどあるでしょうが、意外に知っているようでわかっていなかったことが明らかになることが多いです。
また、研修医時代にいろいろと勉強させて頂いたおかげで、外来や救急などに関してもこの1年間上の先生を頼ったことはほとんどありません。
しかしながら、今までにお話ししたように、僕は整形外科医になる前に、内科や麻酔科、救急など整形外科以外の知識をしっかり身につけておくべきだと思います。
整形外科医になったら勉強したくてもなかなか勉強する機会はありません。整形外科での研修と、整形外科以外の科でどれくらい研修するかは自分のスキルやスタイルに合わせてきちんと考えた方がいいでしょう。
ちなみに今日お話しした、尊敬するそのとき4年目だった先生を自分が4年目のときに追い越していることを目標にしていましたが、5月からはそれが試されます。
3年の差はありますが、長い目でみたら負けていられない年次の相手でもあります。全国にいる整形外科の同期はもちろんですが、5年も離れていない先生にライバルと思ってもらえるくらいの実力をつけていきたいものですね。
そういえば、初期研修病院の決め方などに関しても質問されたことがあるので、また別の機会に記事しようかと思います。
本気でスポーツ医学と運動器診療を学びたい人のために!
- どこにいても(都会でも地方でも)
- 誰でも(医師・理学療法士・鍼灸師・柔道整復師・トレーナー・学生などスポーツに関わる全ての人)
- いつでも(24時間)
利用可能なスポーツセミナー動画配信サービス!!
1週間1円トライアル実施中!!