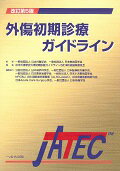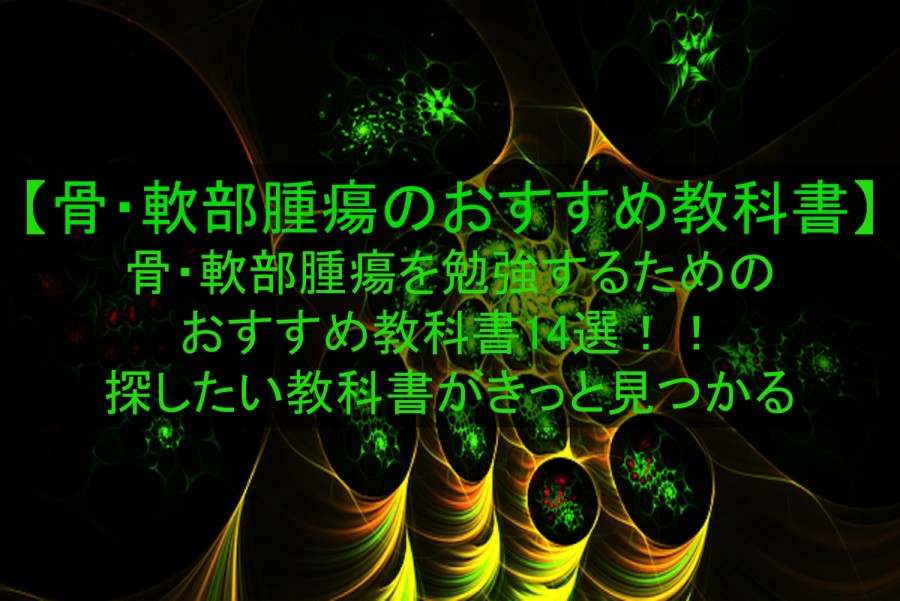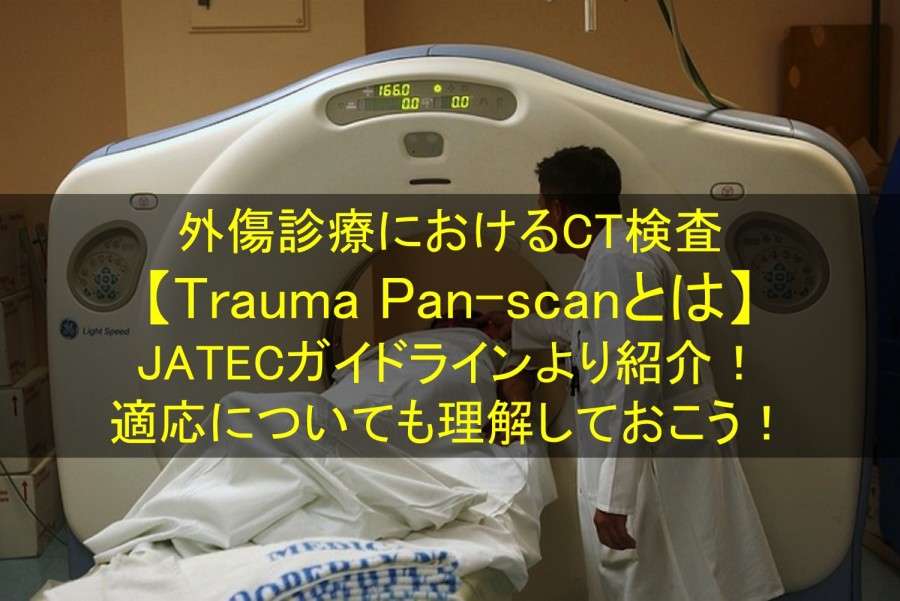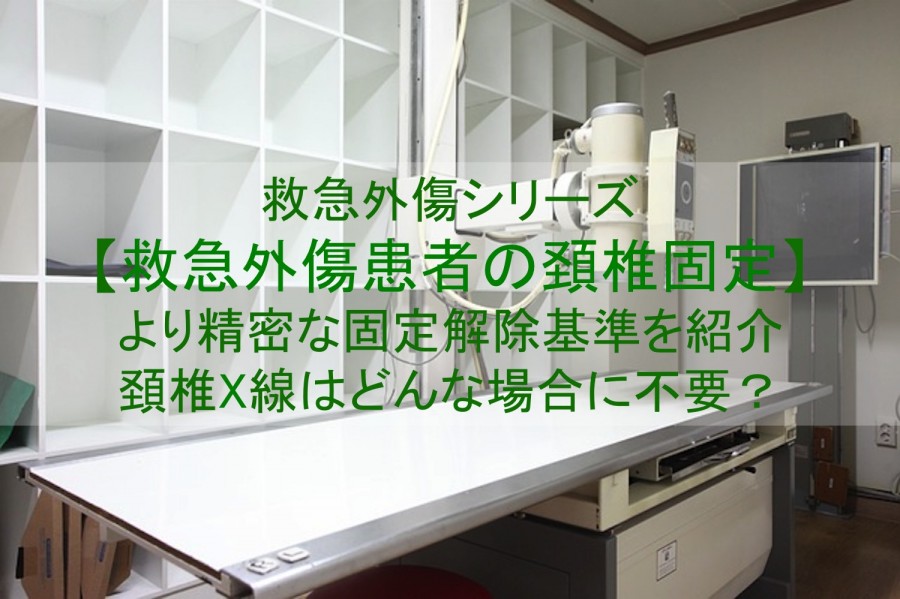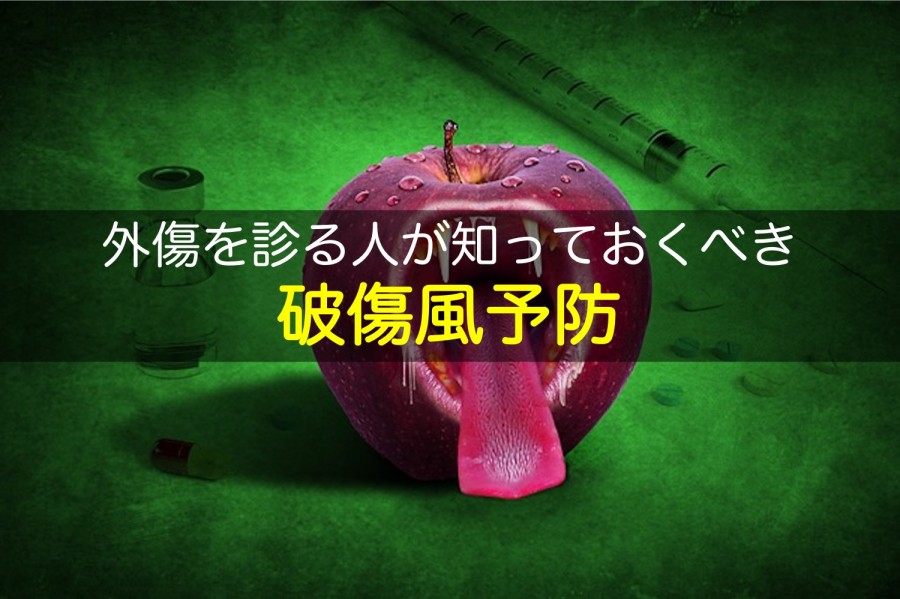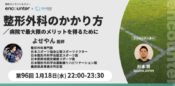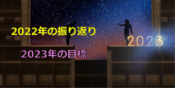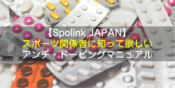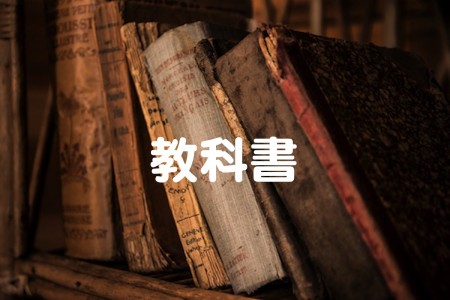生命維持と蘇生|救急外傷診療におけるABCDEを知っておこう!
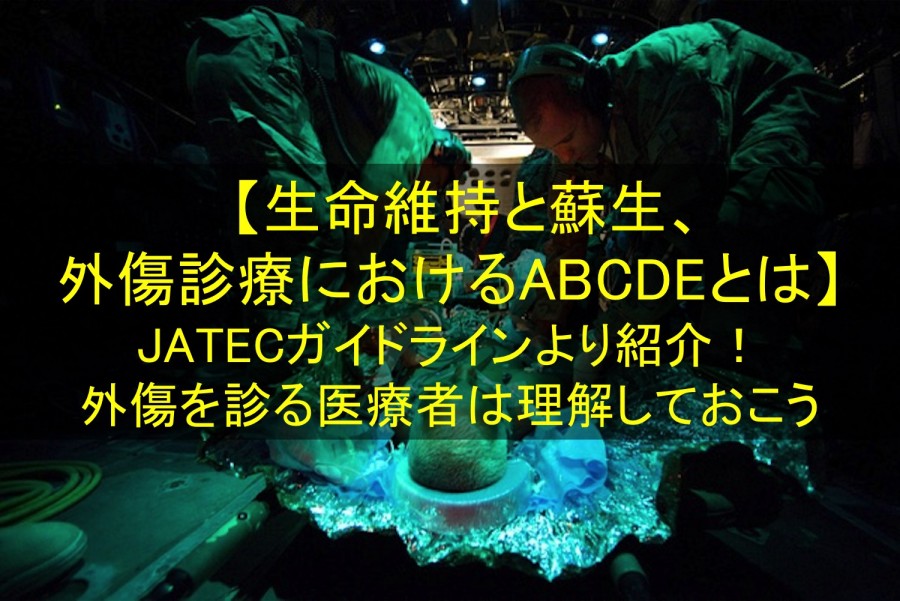
どうも、こんにちは。
若手整形外科医のよせやんです。
 よせやん
よせやん
疲れが溜まっている今日この頃。
しかし、悪天気のせいで患者さん、手術は増える一方ですね。
悪天気のせいでサッカーやフットサルもことごとく中止となり、ストレス発散もできない状況です。笑
さて、今日は昨日に引き続き、救急外傷診療に関する内容です。
切迫する死を回避する診察法を身につけるためには、まず生命維持の整理と蘇生の手順を理解しておく必要があります。
というわけで、今回は生命維持と蘇生、そして救急外傷診療におけるABCDEについてお話しします。
Contents
外傷の死亡
わが国の外傷診療の質は決して高いとは言えない。
最近の研究では、適切な処置を施せば助かると推定される外傷死亡(Preventable Trauma Death:PTD)が、外傷死亡総数の30%を超えているとされている。
そして、この多くが初期診療の診療機能に依存している。
これを改善するには救急医療としての外傷診療システムの構築とこれに関与する医療従事者の診療技術の向上が急務である。
JATECホームページより抜粋
外傷の死亡には、以下の3つの群があります。
- 大血管損傷や致命的脳損傷で即死または数分で死亡する群
- 呼吸障害や出血が原因で2〜3時間後に死亡する群
- 敗血症や多臓器不全で数日以降に死亡する群
この中で、PTD(防ぎ得る死亡)は第2の群によくみられます。
そこで、救急外傷における初期診療の最初の目標は、
この第2群の死亡を防ぐこと、すなわち病院搬送されてきた外傷患者さんを切迫するしから救うこと
にあります。
適切な初期診療を行えば、第2の群における防ぎ得るはずの外傷死を最小限に留めるとともに、第3の群の死亡の減少にも繋がります。( American College of Surgeons Committee on Trauma. 2008 )

生命維持におけるABCDE
この切迫する死を回避する診察法を身につけるためには、生命維持の整理と蘇生の手順を理解しておく必要があります。
生命は、下のように大気中の酸素を取り込み、全身に酸素を供給する一連の仕組みによって維持されています。
特に中枢神経への酸素供給が維持されることで、呼吸・循環の介する生命の輪が形成されています。
- 気道
- 呼吸
- 循環
- 中枢神経
- 環境(体温など)
がサイクルして成り立っています。
気道の開放(Airway)、呼吸管理(Breathing)、循環管理(Circulation)
上記のように、生命維持の仕組みは成り立っていますが、
この輪のどの部位に障害を受けても、生命維持はただちに困難になります。
障害を受けた場合には、ただちにこの連鎖を立て直さなければならず、支持療法の順番は酸素の流れに従うのが理論的でしょう。
すなわち、空気を吸い込む気道が最初であり、次に呼吸系、循環系、中枢神経系といった順番になります。
現時点での医療レベルで支持療法が簡便かつ確実であるのは気道・呼吸器系に対してであり、次が循環系になります。
上気道閉塞による窒息は急速に心停止に至りますが、気道を開放するだけで救命できることを考えればわかりやすいですね。
人工呼吸や胸腔ドレナージなど呼吸系に対する蘇生は迅速かつ確実であるのに対し、止血や輸液・輸血などの循環ん系に対する蘇生はより複雑で時間を要します。
以上より、外傷診療においては、蘇生の順番を気道の開放(Airway)、呼吸管理(Breathing)、循環管理(Circulation)とするのが合理的です。
 よせやん
よせやん
中枢神経障害(Dysfunction of central nervous system)
生命を脅かす中枢神経障害(Dysfunction of central nervous system)に初期診療の段階で確実に対処することは不可能です。
しかし、呼吸・循環の維持は頭蓋外因子による中枢神経系の二次損傷を回避することにつながるため、中枢神経障害に対する支持療法のひとつになります。
低血圧の場合には頭部外傷時の致死率は倍増し、さらに低血圧に低酸素症を合併した場合には、約3倍の致死率となることが報告されています。( Chesnut RM, et al. J Trauma. 1993 )
また、血圧が収縮期で90mmHg以下であることは、脳の二次損傷を引き起こす重要な因子であることが多くの研究で報告されています。(Feliciano DV, et al. Trauma. 6th ed. 2008 )
つまり、呼吸・循環の安定化に加えて、生命を脅かす中枢神経障害を早期に把握しておくことで、頭部外傷に対する迅速で根本的な治療が可能になるわけです。
 よせやん
よせやん
体温の評価と保温(Enviromental control)
着衣のままでは、上述したA・B・C・Dの観察ならびに蘇生は困難であり、不十分なものとなるので、着衣を取って全身を露出(Exposure)する必要があります。
一方、脱衣により患者さんは外気温にさらされ、体温が低下しやすい状況になります。
外傷患者さんは、脱衣などによる熱放射に加えて、ショック時の熱生産の低下、大量輸液や輸血などが原因として加わり、容易に低体温に陥ります。
低体温に陥ると、生理的な代償機構が破綻して蘇生に対する反応が低下し、生命予後が著しく悪くなります。
したがって、診療の初期に低体温を回避することが不可欠であり、生理学的徴候としての体温の評価と保温(Enviromental control)も重要となります。
 よせやん
よせやん
参考図書
この記事の参考図書です。
外傷診療に関わる全ての人が読むべき教科書です。
現在、救急外傷の対応は基本的にこのJATECガイドラインに準じてやっていれば間違いありません。
外傷診療に関わる方はこの教科書で勉強しましょう。
今回のまとめ
以上、今回は生命維持と蘇生に関わるABCDEについてお話ししました。
まとめると、
蘇生の根幹としての気道の開放(A)、呼吸管理(B)、循環管理(C)に、生命を脅かす中枢神経障害(D)と全身の露出と保温(E)を加えて、外傷初期診療における国際的に共通したABCDEアプローチが定式化されている
というわけです。
外傷患者さんを救命するためには、最初に生命維持の生理機能にもとづいたアプローチが重要であり、ABCDEの異常を把握し、この順で蘇生を行っていくことになります。
本気でスポーツ医学と運動器診療を学びたい人のために!
- どこにいても(都会でも地方でも)
- 誰でも(医師・理学療法士・鍼灸師・柔道整復師・トレーナー・学生などスポーツに関わる全ての人)
- いつでも(24時間)
利用可能なスポーツセミナー動画配信サービス!!
1週間1円トライアル実施中!!