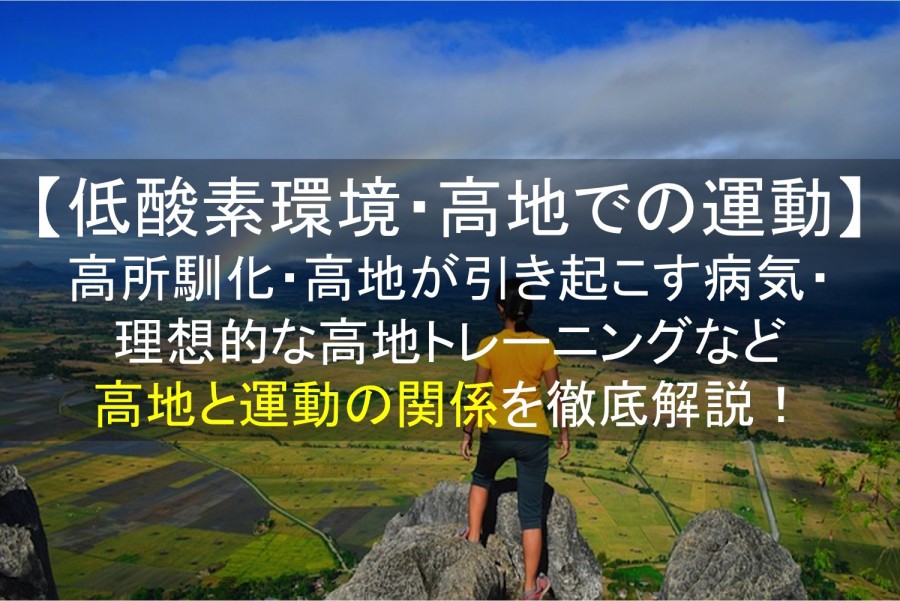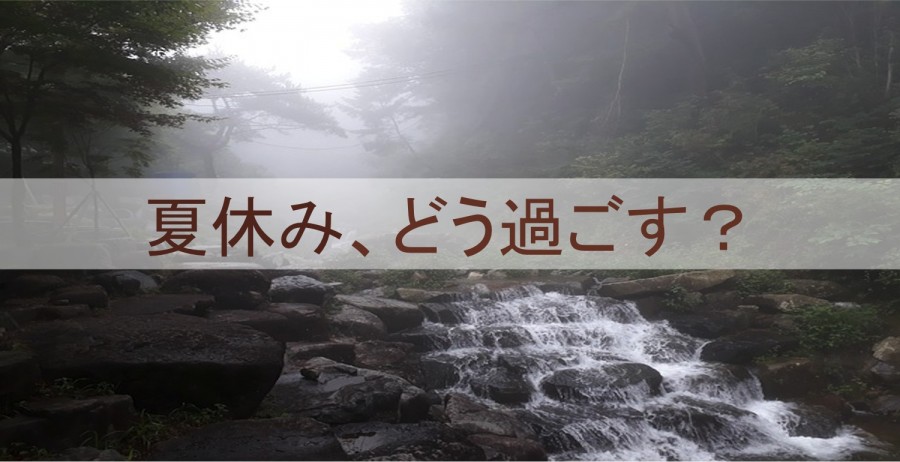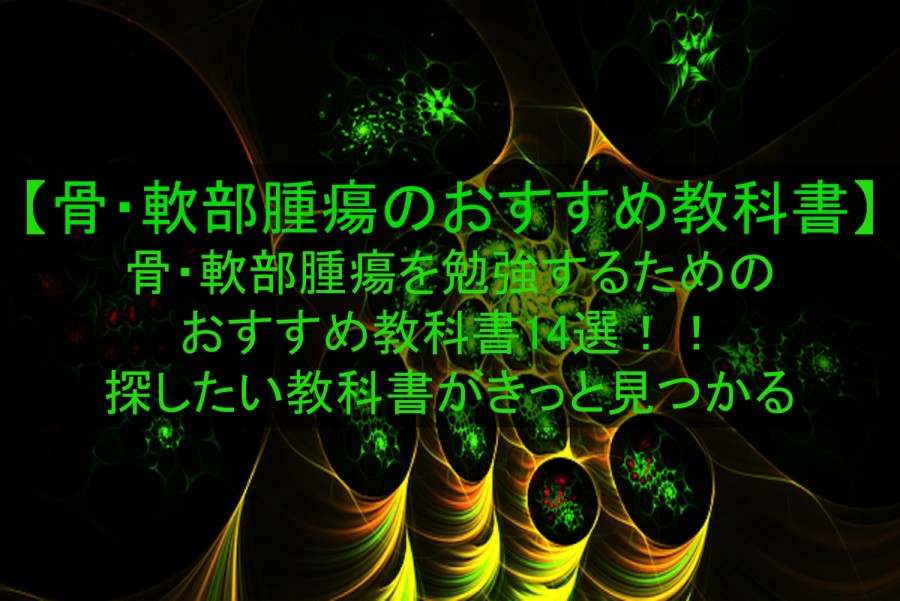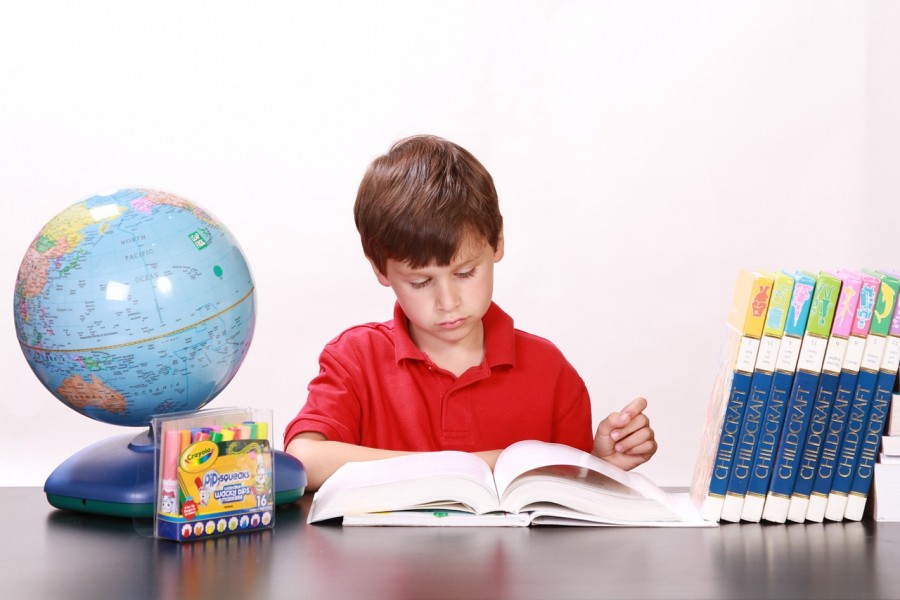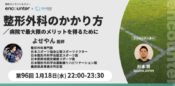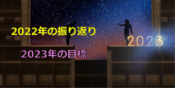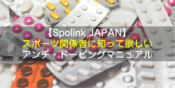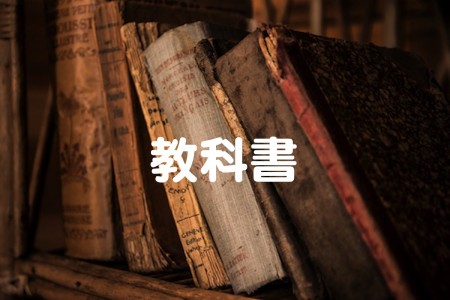水と電解質・輸液を勉強するためのおすすめ教科書|用途別・レベル別に厳選して紹介!
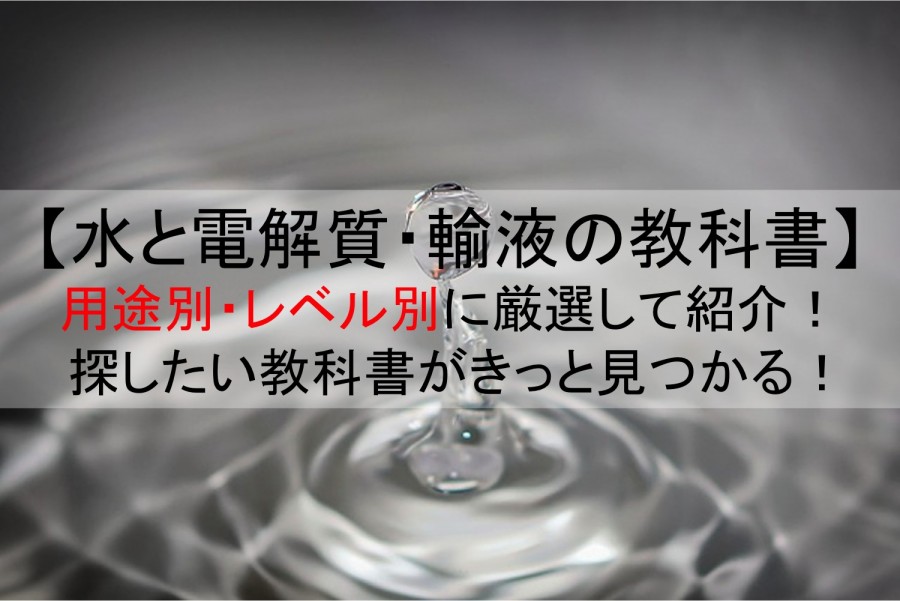
どうも、こんにちは。
若手整形外科医のよせやんです。
 よせやん
よせやん
今日は水と電解質・輸液を勉強するためのおすすめ教科書を紹介します。
水・電解質、輸液の知識は医師であれば何科に進むとしても必ず必要になってきます。
内科はもちろんのこと、外科系の医師であっても周術期の管理で必ず輸液の調整を行わなければならないのです。
しかしながら、水・電解質、輸液はなかなかとっつきにくい分野であり、苦手意識を持っていてきちんと勉強してこなかったという方も少なくないのではないでしょうか。
この記事では、そんな水・電解質、輸液について勉強するためのおすすめ教科書を用途別、レベル別に厳選して紹介していきます。
Contents
しっかりと勉強したい人向けの教科書
まず、輸液についてしっかりと勉強したい人向けの教科書を紹介します。
最初におすすめしたいのがこちらの教科書です。
この教科書は、正しく理論を理解することによってはじめて適切な質・量の輸液を行うことができるという理念のもと、診断と治療、輸液の基本についてわかりやすく解説してくれています。
理解しづらい浸透圧・張度の話から、各種電解質の考え方まで本当にすっきりと整理されて書かれています。
水・電解質をはじめとして輸液に関してしっかり勉強したい人向けのかなりおすすめできる1冊です。僕がこの教科書を読んだのは研修医のときでしたが、それまで電解質をはじめ輸液に苦手意識を持っていたのがこの教科書と出会って改善されたように思います。
 よせやん
よせやん
輸液の教科書を調べていて、これいいな!と思ったのがこちらの教科書です。
INTENSIVISTは、「世界標準の集中治療を誰にでもわかりやすく」をコンセプトに、若手医師の育成や情報交換を目的として発足した日本集中治療教育研究会の活動をベースに年4回発行されています。
この教科書は、輸液・ボリューム管理についてまとめられたものですが、最新のエビデンスに基づいて、現在わかっていることとわかっていないことを検証し徹底的に解説してくれています。
これからの輸液・ボリューム管理に関する現在のスタンダードを知るには非常に有用でないかと思います。
 よせやん
よせやん
入門者・時間がない人向け
続いて、輸液に関する入門者や時間がないから手っ取り早く輸液の全体像を掴みたいという方におすすめの教科書を紹介します。
入門書として絶対的におすすめなのがこの教科書です。非常にコンパクトな教科書ではありますが、理解しにくい電解質・酸塩基平衡がわかりやすく解説されています。
電解質・酸塩基平衡を考えるときに、こういう見方をしなくてはいけないのかということが学べます。
確かに、水と電解質や輸液は非常にとっつきにくい分野だと思うので、最初から難しい教科書を読むよりも、こういった入門書を読んだ方が早く理解できるようになるのではないかと思います。
 よせやん
よせやん
特に、医学生や初期研修医の先生におすすめです。
上の教科書よりももっともっと時間をかけずに輸液の全貌を掴みたいという方にはこの教科書がおすすめです。
僕は医師国家試験が終わって初期研修医になるまでの期間にこの教科書を読みましたが、その気になれば1日あれば余裕で読めてしまうくらいのボリュームです。
 よせやん
よせやん
内容的に古い部分もあると思いますが、根本となる部分は昔も今も変わりないと思うので輸液の基礎を学ぶうえでは全く問題ないと思います。
同じような教科書としてこちらの教科書もおすすめです。
輸液を理解するための必須知識と処方の根拠が簡単なQ&Aでわかるように書かれています。
また、この教科書を買うとブラウザーで動く計算ソフトがもらえるので、これを使いながら実臨床に活かすための考え方を学び応用力を鍛えることができます。
実臨床向けの教科書
続いて、輸液の教科書の中でも実践向けの教科書を紹介します。
輸液をテーマにした臨床の場面に即したまさに実践的な教科書です。
実臨床での輸液で、特に注意して対応しなくてはいけないのは救急やICUの患者さんなのは言うまでもないでしょう。
全身状態が不安定な患者さんに対する輸液の量や種類を間違えるとそれが命取りになることもあります。
そんな救急やICUの患者さんの対応をするときにそばに置いておくと心強い教科書だと思います。
この教科書では、急性期と慢性期の体液バランスの違いを病態生理をふまえながら病態ごとに解説してくれており、輸液のほか、利尿薬や循環作動薬の病態による使い分けや、呼吸・循環を中心とした全身管理に役立つかと思います。
 よせやん
よせやん
もう1冊輸液の実臨床向けの教科書を紹介しておきます。
これだけはわかっておきたい輸液の基本や覚えておくと必ず役立つ基礎知識を解説してくれているのはもちろんですが、診療科・疾患ごとの輸液のポイントが書かれている点が非常にいいところです。
具体的には、輸液が必要かどうかの判断、輸液を止めるタイミング、具体的にどういう処方をするのかを商品名をあげて実践的に解説していくれています。
初期研修医の先生は、ローテートする科のところを読んでおくことで各科での輸液に自信が持てるようになるでしょう。
 よせやん
よせやん
周術期管理
次に、周術期の輸液について勉強するための教科書を紹介します。
周術期における輸液は、麻酔科医はもちろんのこと、外科系の医師ならば必ず知っておかなくてはいけません。
外科系の医師で周術期の輸液に関して理解していないのは相当やばいです!
自分が周術期の輸液に関してきちんと勉強したのは整形外科医になってからでしたが、上の言葉に少しでもドキッとしたあなたはここで紹介する教科書で一度きちんと勉強しておきましょう。
 よせやん
よせやん
周術期の輸液を勉強するうえでおすすめなのがこちらの教科書です。
外科系医師にとって重要な周術期の循環管理に焦点を当て、術前評価、術前・術中・術後管理や術中のモニターなどについて、最新のエビデンスを盛り込みながら分かりやすく解説してくれています。
麻酔科の先生向けの教科書なので、経食道心エコーやIABPの活用法などの外科はあまり関わらない部分にも触れられていますが、単なるマニュアル本とは異なり、非常に質の高い実践的で周術期管理としての輸液について高いレベルで学ぶことができます。
周術期の輸液を学ぶための教科書をもう1冊。
この教科書では、周術期の輸液に関する最新の研究を、基礎編と臨床編に分けて紹介しています。
どのような考え方で輸液療法を考えるべきかを各分野の専門家が示しており、輸液と循環血液量、周術期の水動態、敗血症と輸液療法など、臨床にすぐ役立つテーマが収録されています。
参考文献も豊富で最新の情報が記載されているこの教科書を読んでおけば、周術期の輸液製剤の選択や投与速度・量などを自信を持って決めれるようになるでしょう。
 よせやん
よせやん
ポケットマニュアル
最後に意外に使える輸液のポケットマニュアルを紹介しておきます。
これは、臨床の現場で必要とする情報が網羅された、ベッドサイドで利用できるハンディーな輸液マニュアルです。
簡潔明瞭で実践的なマニュアルですが、ただ単に処方例が載っているだけではなくて、輸液の考え方から体液量の評価方法、診断のエッセンスまできれいにまとめてある。
「こんな本が欲しかった」「めっちゃ使える」という感想を持つであろう非常に便利で有用なポケットマニュアルです。
 よせやん
よせやん
おわりに
以上、今回は水と電解質・輸液を勉強するためのおすすめ教科書を厳選して紹介しました。
なかなかとっつきにくいくせに医師なら必ず知っておかなければならない水と電解質、輸液という分野をここで紹介した教科書を参考にして勉強し、自信を持って扱えるようになりましょう。
水と電解質、輸液を勉強したいと思っている方の参考になれば幸いです。
本気でスポーツ医学と運動器診療を学びたい人のために!
- どこにいても(都会でも地方でも)
- 誰でも(医師・理学療法士・鍼灸師・柔道整復師・トレーナー・学生などスポーツに関わる全ての人)
- いつでも(24時間)
利用可能なスポーツセミナー動画配信サービス!!
1週間1円トライアル実施中!!