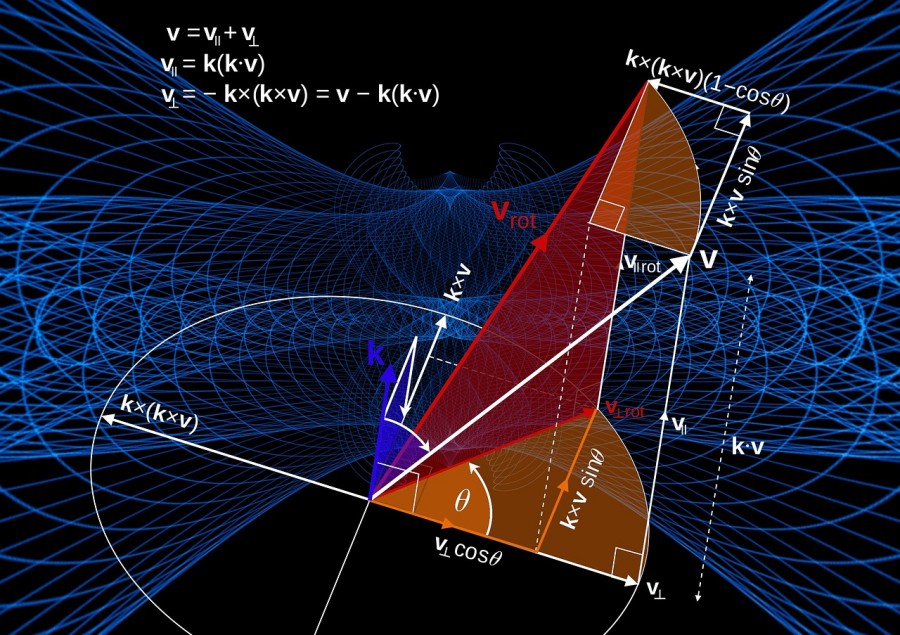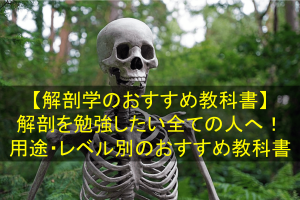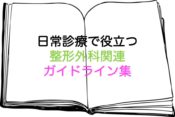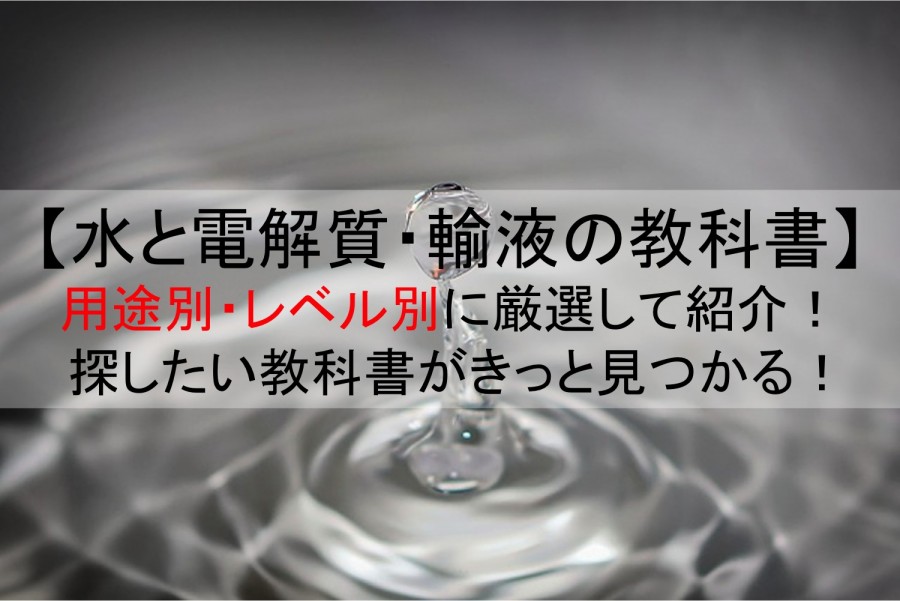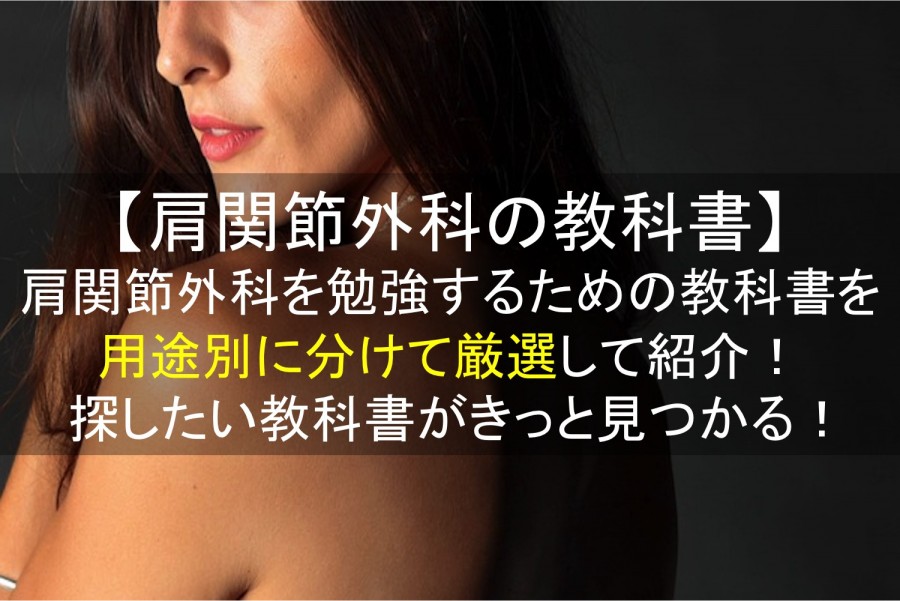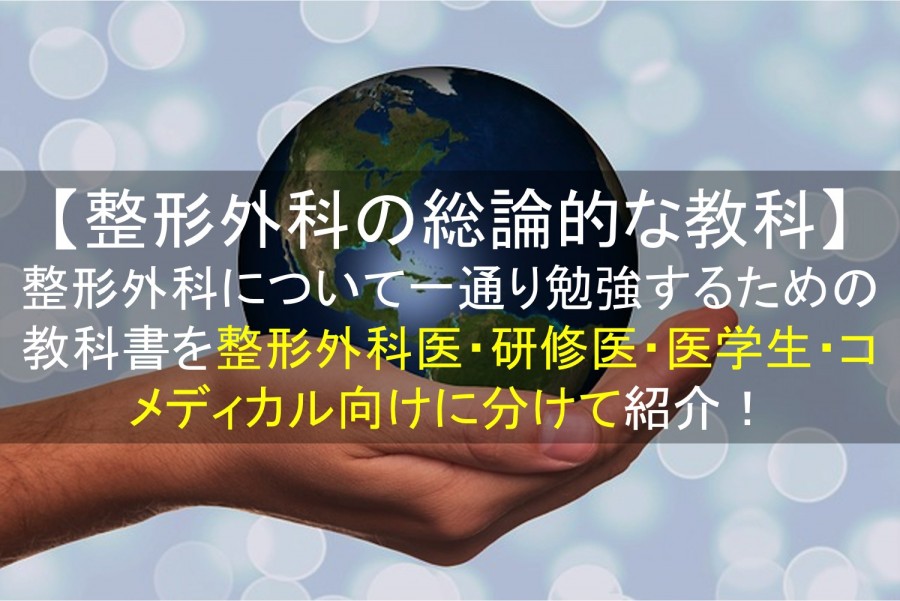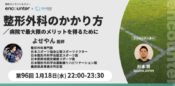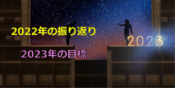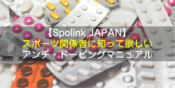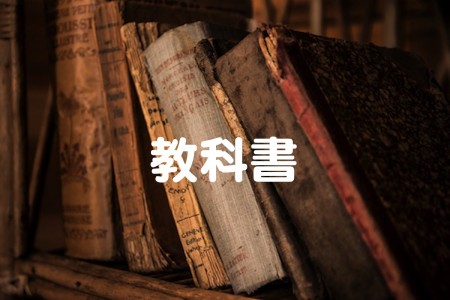薬理学のおすすめ教科書|用途、レベル別におすすめ教科書を紹介!

どうも、こんにちは。
若手整形外科医のよせやんです。
先日、看護学校に講師として授業をしに行きました。
講義の内容は運動器についてです。
人に教えると言うのはなかなか難しいものですね。
というか、学会発表もそうですが、まず人前で話すのが苦手です。
整形外科医として看護師さんに知っておいて欲しいことを中心に、話しやすいスポーツ関連のことをメインに話そうと思ってます。
さて、今日は教科書紹介のシリーズです。ご要望があったので、医学の基礎科目の教科書を順に紹介していこうと思います。
今回は薬理学のおすすめ教科書を紹介していこうと思います。
用途別・レベル別に教科書を紹介していきます。
Contents
はじめに
臨床の現場に出ると、嫌でも薬理学の知識が必要になります。
治療に用いる薬ですが、どうしてその病気に対して効果があるのかという作用機序を理解しておくことはとても大切です。また、副作用・禁忌・相互作用などを知っておかないと薬は毒にもなり得ます。
薬理学を理解する上で、生理学や生化学の知識も必要になってくるので、併せてしっかりと勉強しておくとよいでしょう。
 よせやん
よせやん
今日はこの薬理学のおすすめ教科書を紹介していきます。
よく使われている教科書、しっかりと勉強したい人向けの教科書、時間がない・入門書として導入に使う場合の教科書にわけて紹介していきますので、自分に合った用途やレベルの教科書を見つける参考にして頂けたらと思います。
よく使われている教科書
まず、医学生によく使われている教科書を紹介します。
多くの医学生に使われている代表的な和書の教科書です。基礎から標準レベルを網羅していて、非常に分かりやすいです。
洋書の薬理学の教科書にはすばらしいものが多く、世界基準で学ぶことには適していますが、当然のことながら洋書では日本では使われていない薬などが書かれていることもあります。
和書で1番おすすめできるのはこのNEW薬理学でしょう。
続いておすすめなのがこのイラストレイテッド薬理学です。原著は英語版の Lippincott Illustrated Reviews: Pharmacology![]() です。
です。
イラストレイテッド薬理学は名前の通りわかりやすいイラストが多く使われており、非常に読みやすくわかりやすいと思います。個人的にはイラストレイテッド薬理学をおすすめします。
しっかりと勉強したい人向け
続いて、できる医学生を目指す方や意識の高い方におすすめしたい教科書です。
世界的に定評のある薬理学書Basic & Clinical Pharmacology![]() の日本語版です。
の日本語版です。
薬理学の入門・基礎から、関連臨床分野、日常診療・薬剤業務に必須の臨床薬理学や臨床薬学までを網羅しています。世界基準でしっかりと勉強しておきたいならばカッツングでしょう。
また第10版では、日本での実情をふまえた訳注や日本で入手可能な薬剤リストが加えられているのもうれしいところです。英語が得意な方は、原書で勉強するとよいでしょう。
病態と薬理を結び付けて開設されている本当にすばらしい教科書です。
タイトルにもなっていますが、実際にハーバード大学で使用されているテキストです。
簡明なイラストを豊富に用いて、各病態のメカニズムを生化学・生理学・病態生理学に基づいて整理し、個々の薬物が標的とする分子機序が説明されています。
生理学を用いて薬理の作用基序をきちんと理解することができ、病態に応じた薬剤の分類と薬理がよくまとめられていたり症例も提示されているので、薬理学の深い理解と臨床で応用できる知識を身につけられると思います。
ぜひとも、読んで頂きたいおすすめの教科書です。
英語が得意な人は原書のPrinciples of Pharmacology![]() で勉強してください。
で勉強してください。
時間がない人向け
続いて、生理学をゆっくり勉強する時間がない場合や、上記の本で勉強する前の足がかりとして使う場合の教科書を紹介します。
内容は薄くなりますが、時間をあまりかけずに生理学のおおまかな内容を理解する手助けになると思うので参考にしてみてください。
上で紹介したカッツング薬理学のエッセンシャル版です。
薬理学とその関連臨床領域の必須項目の明解な説明と応用力熟成のための厳選された1,000を超える問題から構成されています。
問題を解きながら勉強するのが好きな人には向いていると思います。
「病態生理から見た臨床薬の使い方」をベースに、臨床現場で必要となる項目を中心にイラスト主体でわかりやすく解説されています。
学問としての薬理学はなるべく排除するように書かれているため、薬理学に苦手意識のある方でもとっつきやすい教科書です。
薬理学の入門書としてならこちらもおすすめです。
薬理学に苦手意識のある方が導入に読むのに利用するのもいいかもしれません。ハンドブック
最後に、治療薬のハンドブックを紹介しておきます。
臨床では、聞いたことのない薬剤の名前を耳にすることも多いかと思います。
そんなときは、これらの教科書で毎回きちんとチェックしましょう。
これらの本は毎年発刊されているので、可能なら毎年更新していくべきでしょう。
言わずと知れた有名な教科書ですね。
病院の各病棟や各診察室に置かれていることが多いのではないでしょうか。
医師や薬剤師ならポケットに入れておくべきハンドブックです。
臨床に必要不可欠な情報が、非常にコンパクトにまとまっています。添付文書だけではわからない「薬の個性」や「他の薬との違い」が、きちんと記されており、ものすごく役に立つことでしょう。
非常におすすめできるハンドブックです。
ポケットに入れておく医薬品集としてはこちらでもいいと思います。
見やすい表組みレイアウトと読みやすい大きな文字で書かれており、読みやすいです。
おわりに
以上、今回は薬理学の教科書を紹介してきました。
患者さんを治療していく上で、薬に関する知識は必ず必要です。
薬理学は医師・看護師・薬剤師は必ず学ばなければならない学問の一つですので、働き出してからでももちろんいいですが、せっかくなら時間のある学生のうちにしっかりと勉強しておきましょう。
 よせやん
よせやん
多くの医学生が持っている教科書、できる医学生を目指す方や意識の高い方におすすめの教科書、そして、時間がない場合や入門書として使う場合の教科書にわけて紹介しましたので、ご自分の用途やレベルに合わせて選んでみて下さい。
この記事が教科書を選ぶときの参考になったら幸いです。
本気でスポーツ医学と運動器診療を学びたい人のために!
- どこにいても(都会でも地方でも)
- 誰でも(医師・理学療法士・鍼灸師・柔道整復師・トレーナー・学生などスポーツに関わる全ての人)
- いつでも(24時間)
利用可能なスポーツセミナー動画配信サービス!!
1週間1円トライアル実施中!!