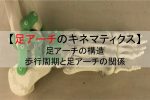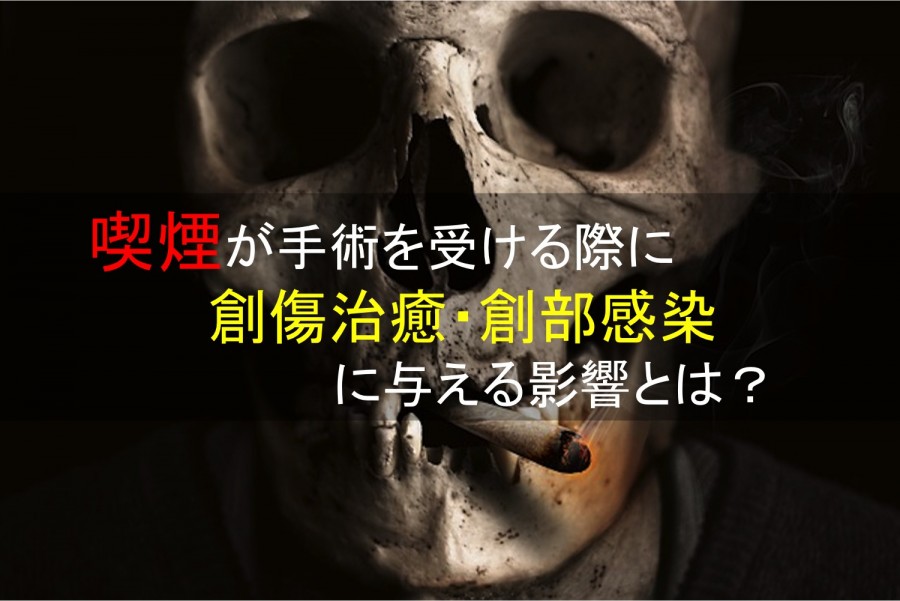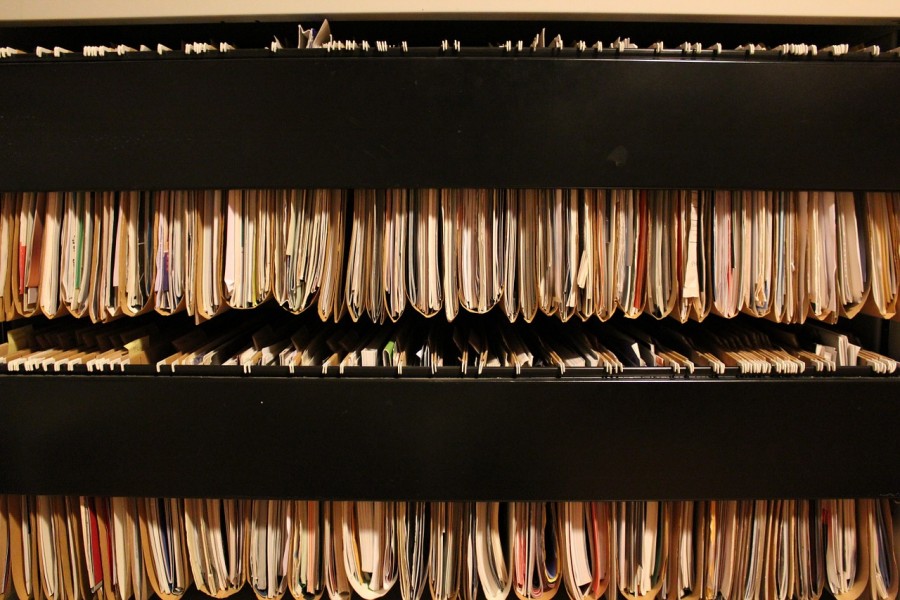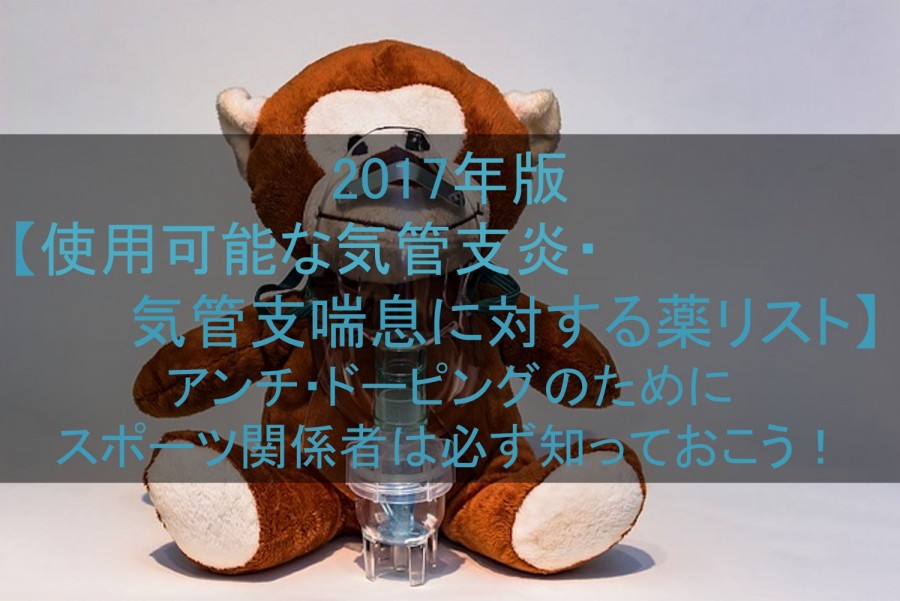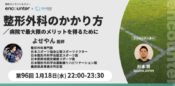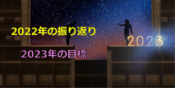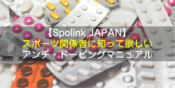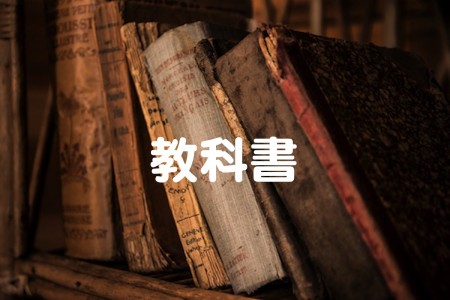足アーチにおける筋肉の役割とは|後脛骨筋・長腓骨筋が足アーチに及ぼす影響を解説!

どうも、こんにちは。
若手整形外科医のよせやんです。
 よせやん
よせやん
本日は足アーチにおける筋肉の役割についてお話しします。
足アーチに関わることがわかっている筋は主に2つあります。
- 後脛骨筋
- 長腓骨筋
この記事では、これらの筋が足アーチに及ぼす影響について解説していきましょう。
足の機能はとても難しくマニアックな領域かもしれませんが、勉強すると意外に面白い分野です。
ぜひ興味を持って頂けたら幸いです。
Contents
後脛骨筋と足アーチ
近年、後脛骨筋腱が足アーチに対して重要な働きをしていることが報告され、注目を浴びています。(Johnson KA., et al. Clin Orthop Relat Res. 1989)
後脛骨筋腱の解剖
まず、後脛骨筋の解剖を紹介しておきましょう。
- 起始:腓骨、下腿骨間膜
- 停止:舟状骨、3つの楔状骨、立方骨、第2〜4中足骨底面
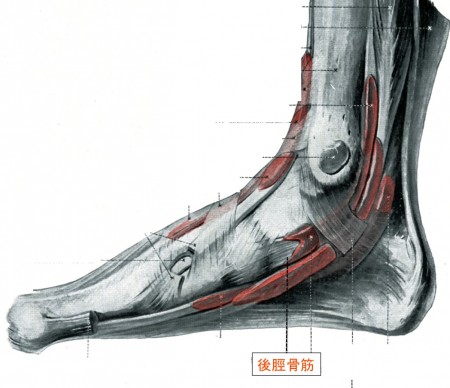
後脛骨筋の足アーチに及ぼす影響
後脛骨筋は、踵接地時と立脚期中期に収縮することがわかっています。
Elftmanらは、その解剖学的特徴から後脛骨筋が緊張すると、足部回外によってChopart関節における距舟関節と踵立方関節の運動軸が平行でなくなり、stiffness(剛性)の強い硬い(rigid)足となり、逆に、後脛骨筋が弛緩すると足部回内によってChopart関節における距舟関節と踵立方関節の運動軸が平行となってstiffnessの弱い柔軟性のある(flexible)足となるとの仮説を立てました。(Elftman H. Clin Orthop. 1960)
橋本らは、この事実を確かめるため、局所麻酔下に脛骨、距骨、踵骨にマーカーをつけたピンを打った状態での歩行を三次元動態解析し、踵接地時には距骨下関節が内がえしをしており、その後、外がえしとなり、立脚期中期に再び内がえしとなることを報告し、Elftmanの仮説を検証しています。(Arndt A, et al. Foot Ankle Int. 2004)
長腓骨筋と足アーチ
また、足底において後脛骨筋と交叉する長腓骨筋も最近注目され、その足アーチに対する影響も調べられています。
長腓骨筋の解剖
- 起始:脛骨外側顆、腓骨近位2/3
- 停止:内側楔状骨と第1中足骨底部
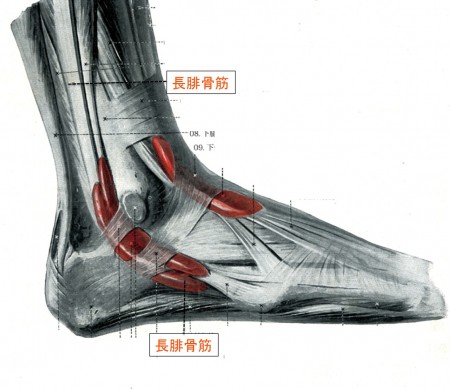
長腓骨筋の足アーチに及ぼす影響
では、長腓骨筋は足アーチにどのような影響を与えているのでしょうか。
橋本は、cadaverを用いた実験より、長腓骨筋が緊張すると足部を回内することによって、足部のstiffnessを減少させることを示しています。(橋本健史. 関節外科. 2015)
すなわち、
長腓骨筋は後脛骨筋と拮抗的に働く
ことがわかったのです。
まとめると
後脛骨筋、長腓骨筋の足アーチへ及ぼす影響をまとめてみましょう。
これら2つの筋は、後脛骨筋が足アーチを高めて足部のstiffnessを増大(rigidである状態)させ、長腓骨筋が足アーチを減少させて足部のstiffnessを減少(flexibleである状態)させているのです。
続いて、歩行周期との関係についてはどうでしょうか。
歩行周期においては、まず踵接地時に後脛骨筋が働いて足アーチを高めて足のstiffnessを増大させ、接地時の衝撃に備えます。次に体重負荷によりtruss mechanismが働き、足アーチは低下していきます。
踵離地とともに再び後脛骨筋が働き、足アーチを高めて足部のstiffnessを増大させ、前方推進力を地面に効率的に伝えます。このとき、同時に足趾も背屈してwidlass mechanismを働かせてこの過程を助けますが、長腓骨筋も同時に働き、後脛骨筋の働きを制御していくことになります。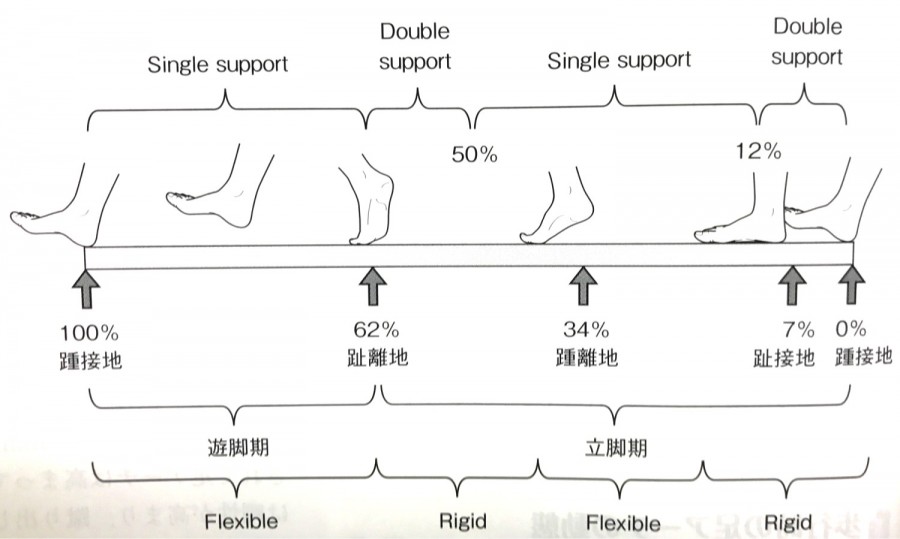
おわりに
以上、今回は足アーチにおける筋の役割についてお話ししました。
実は、足アーチのキネマティクスについては、まだ未解明な部分が多くあります。
足アーチの動的機能に他の腓腹筋や長母趾屈筋、長趾屈筋などがどのように働いているか、足アーチの制御神経系がどうなっているのかなどの解明が進めば、治療もまた変わってくることになるのでしょう。
本気でスポーツ医学と運動器診療を学びたい人のために!
- どこにいても(都会でも地方でも)
- 誰でも(医師・理学療法士・鍼灸師・柔道整復師・トレーナー・学生などスポーツに関わる全ての人)
- いつでも(24時間)
利用可能なスポーツセミナー動画配信サービス!!
1週間1円トライアル実施中!!