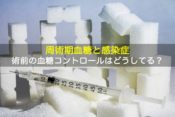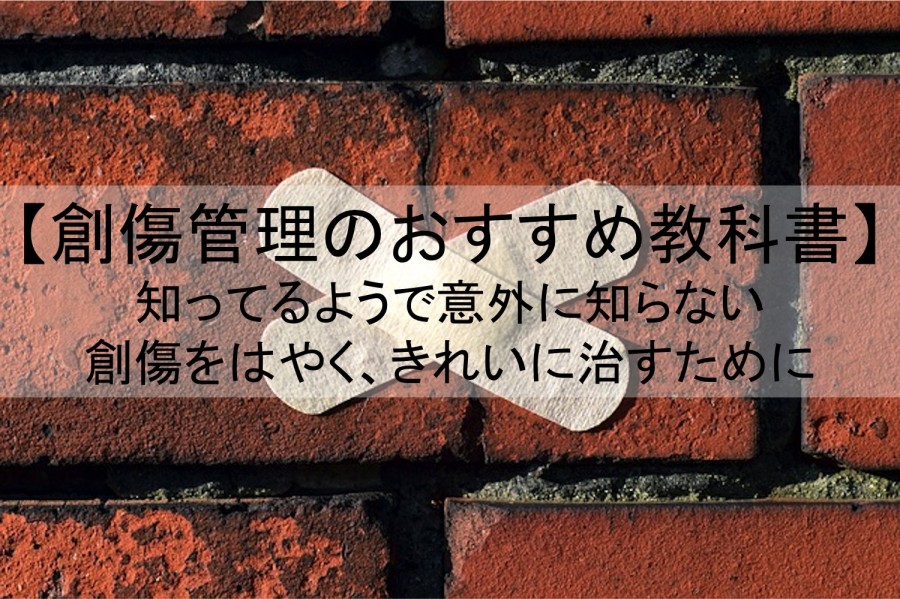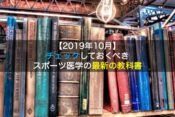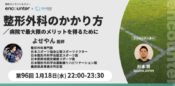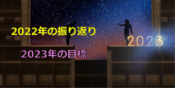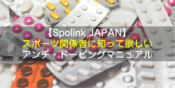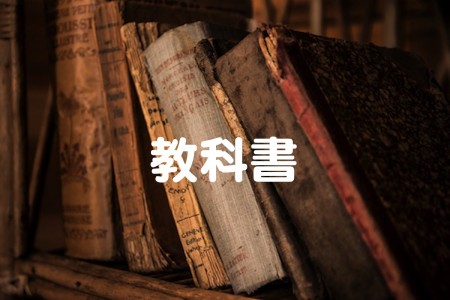整形外科関連の診療・予防ガイドラインをまとめて紹介|整形外科医・運動器診療に携わる方は要チェック!
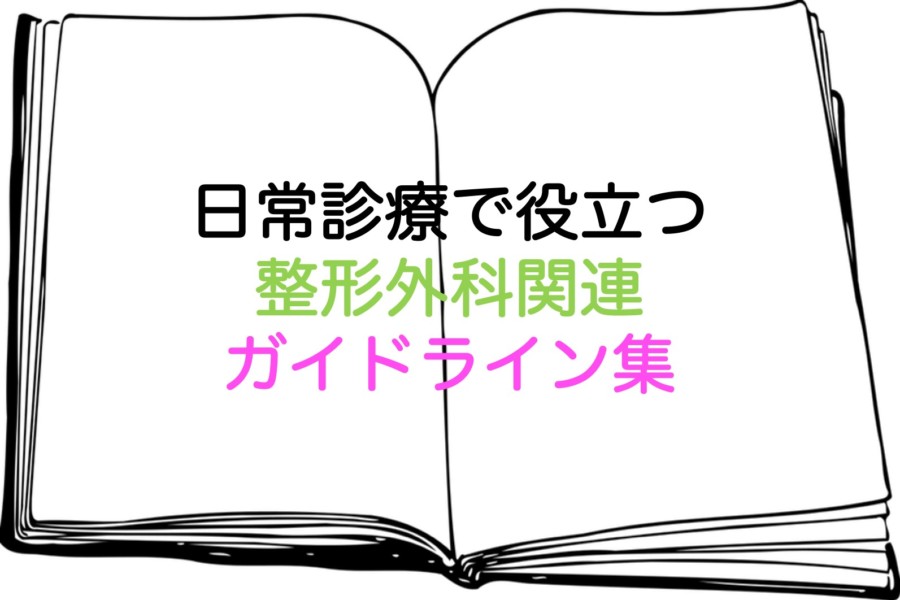
どうも、こんにちは。
若手整形外科医のよせやんです。
 よせやん
よせやん
先週末は日本整形外科学会学術総会に参加してきました。
今回も学会の書籍販売コーナーで新しいよい教科書はないかな〜と見ていたのですが、2019年に新しく2つのガイドラインが発刊されていました。
2019年に発刊されたのは腰痛診療とACL損傷診療のガイドラインで、僕も今回ページをめくって読んでみましたが、日常診療でこの疾患の治療のスタンダードを知りたい!とかエビデンスってどうなのかな?と思った時に非常に参考になりそうなものばかりで非常に興味深かったです。
というわけで、僕自身が改めて日常診療でよく出会う疾患に関してはガイドラインを知っておきたいなと思って、整形外科のガイドラインとしてどんなものが発刊されているのか調べてみました。
というわけで、今回は整形外科関連のガイドラインを一挙大紹介しようと思います。
整形外科医の先生は日常診療において非常にためになると思いますので、気になる疾患に関しては揃えてみてはいかがでしょうか。
また、整形外科医以外の運動器診療に携わる先生も整形外科医がどのような診療を行うのがスタンダードなのか知っておくことは非常に参考になることがあるかと思います。是非、一度読んでみてはいかがでしょうか。
 よせやん
よせやん
Contents
脆弱性骨折のガイドライン
まず、整形外科医が日常診療で出会うことがかなり多い脆弱性骨折の診療ガイドラインです。
整形外科医や整形外科で研修した研修医の先生はよくわかるかと思いますが、高齢化が進んでいる現在の日本において脆弱性骨折はほぼ毎日のように出会い診療しなければいけないものになっています。
骨粗鬆症のある方が尻もちをつけば椎体骨折、横に倒れて受け身を取れないと上腕骨近位部骨折や大腿骨近位部骨折、受け身をとって手をつくと橈骨遠位端骨折というのがまさに脆弱性骨折の王道ですね。
整形外科医は当然のこと、運動器診療に携わる方は脆弱性骨折である以下の疾患のガイドラインは知っておいて損はないと思います。
 よせやん
よせやん
椎体骨折
日本整形外科学会・日本脊椎脊髄病学会・日本骨折治療学会・日本骨形態計測学会・日本骨代謝学会・日本骨粗鬆症学会・日本医学放射線学会の7学会合同による委員会が作成したガイドラインです。
椎体骨折は必ず診療することになるcommon diseaseなので、若手医師の方はきちんと勉強しておくといいでしょう。
大腿骨近位部骨折
日本整形外科学会・日本骨折治療学会監修のガイドラインです。
ただ2011年発刊と少し古いので、個人的には以下の本の方がオススメです。
若手の先生はこちらの教科書は必ず持っておくといいと思います。
大腿骨近位部骨折も必ず診療することになる疾患の一つです。
橈骨遠位端骨折
橈骨遠位端骨折は2017年に改定版が出ました。
日本整形外科学会・日本手外科学会が監修のガイドラインです。
橈骨遠位端骨折も日常診療で必ず出会う疾患の一つです。
骨粗鬆症
そして、一緒に脆弱性骨折と併せて抑えておきたいのが骨粗鬆症の予防と治療です。
脆弱性骨折の最も多い原因は骨粗鬆症ですので、脆弱性骨折の予防は極めて大切ですし、脆弱性骨折で治療する患者さんに対しては併せて骨粗鬆症に対しても治療介入しなくてはなりません。こちらは日本骨粗鬆症学会・日本骨代謝学会が監修のガイドラインです。
脊椎外科関連のガイドライン
次に、整形外科でもメジャーな分野である脊椎外科関連のガイドラインです。
頚部痛や腰痛、四肢の末梢神経症状を有する患者さんは極めて多く、日常診療で出会わない日はないでしょう。
個人的には、腰痛診療・頚椎症性脊髄症・腰部脊柱管狭窄症・椎体骨折は抑えておくべきかなと思います。
 よせやん
よせやん
腰痛診療
こちらは2019年に改定されたばかりの腰痛診療のガイドラインです。
日本整形外科学会、日本腰痛学会が監修したガイドラインです。
頚椎症性脊髄症
日本整形外科学会・日本脊椎脊髄病学会が監修のガイドラインです。
頚椎後縦靱帯骨化症
日本整形外科学会・日本脊椎脊髄病学会が監修のガイドラインです。
腰部脊柱間狭窄症
日本整形外科学会・日本脊椎脊髄病学会が監修のガイドラインです。
腰椎椎間板ヘルニア
日本整形外科学会・日本脊椎脊髄病学会が監修のガイドラインです。
椎体骨折
再掲になりますが、日本整形外科学会・日本脊椎脊髄病学会・日本骨折治療学会・日本骨形態計測学会・日本骨代謝学会・日本骨粗鬆症学会・日本医学放射線学会の7学会合同による委員会が作成したガイドラインです。
四肢の疾患
続いて、四肢の疾患に関するガイドラインです。
変形性股関節症と変形性膝関節症も日常診療でかなり出会うことの多い疾患です。
変形性膝関節症のものは発刊されていませんが、変形性股関節症のガイドラインは知っておくとよいと思います。
ACL損傷と外反母趾は少しマニアックな領域になるので、ガイドラインはその分野の専門の方や興味のある方だけでよいかもしれません。
 よせやん
よせやん
変形性股関節症
日本整形外科学会・日本股関節学会が監修のガイドラインです。
前十字靭帯(ACL)損傷
こちらも2019年に改訂第3版が出版されました。
日本整形外科学会、日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会(JOSKAS)が監修のガイドラインです。
外反母趾
日本整形外科学会・日本足の外科学会の監修のガイドラインです。
その他のガイドライン
最後に、上記で紹介した以外のガイドラインをまとめて紹介します。
整形外科医であれば、これら3つのガイドラインは知っておいた方がいいかと思います。おそらく日常診療でも迷うことの多い整形外科関連の疾患ではないでしょうか。
 よせやん
よせやん
軟部腫瘍
軟部腫瘍は一般整形外科医でもちょくちょく外来診療で出くわす疾患です。
最低限のルールは一般整形外科医も知っておくべきかと思います。日本整形外科学会が監修のガイドラインです。
症候性静脈血栓塞栓症
人工関節や下肢の骨折手術はもちろんのこと、どこかを痛めてベッド上安静にしているだけで罹患する可能性があります。
こちらも日本整形外科学会監修のガイドラインです。
骨・感染術後感染予防
整形外科領域の感染予防については整形外科医は必ず知っておかなくてはいけません。
非常に大切な分野であることはもはや異論ないでしょう。
こちらは日本整形外科学会、日本骨・関節感染症学会が監修のガイドラインです。
おわりに
以上、今回は整形外科関連のガイドラインをまとめて紹介しました。
日常診療でこの疾患の治療のスタンダードを知りたい!とかエビデンスってどうなのかな?と思った時に非常に参考になるので、整形外科医の先生は気になる疾患に関しては揃えてみてはいかがでしょうか。
また、整形外科医以外の運動器診療に携わる先生も整形外科医がどのような診療を行うのがスタンダードなのか知っておくことは非常に参考になることがあるかと思います。
ガイドラインを知りたい方の参考になれば幸いです。
本気でスポーツ医学と運動器診療を学びたい人のために!
- どこにいても(都会でも地方でも)
- 誰でも(医師・理学療法士・鍼灸師・柔道整復師・トレーナー・学生などスポーツに関わる全ての人)
- いつでも(24時間)
利用可能なスポーツセミナー動画配信サービス!!
1週間1円トライアル実施中!!