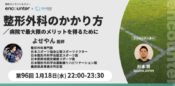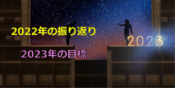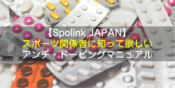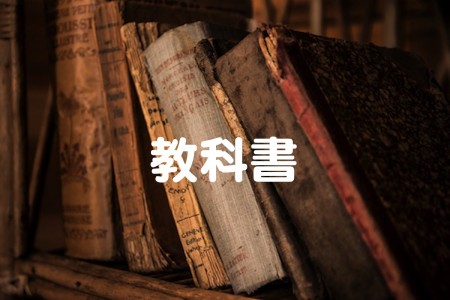スポーツドクターとしてスポーツ選手のためにできること

どうも、こんにちは。
若手整形外科医のよせやんです。
ブログを始めてから初めてこんなに更新しない期間ができてしまいました。
体調を崩していたわけではありませんが、仕事とフットサルで疲れ果てていたのと、病棟の歓送迎会などが重なって時間がありませんでした。
5月から新しい病院に勤務するようになり、また忙しい充実した日々が始まりました。
今の課題はどれだけ仕事を早く終わらせて、どれだけ自分の勉強や臨床研究、論文の時間を確保できるかです。
忙しくしているのは好きだし、できること、診れる疾患が増えてくる喜びを日々感じていますが、疲れてしまうとソファーに座ったまま寝てしまったりします。
そんな中でも社会人サッカーとフットサルは続けてます。
練習はいつも平日の夜にあるので、その日は仕事を早く切り上げて練習へ。フットサルの練習は本当に厳しい。
いつも自分では頑張っているつもりだけど、やっぱり自分で頑張るというのは難しく、まだまだ頑張りが十分じゃないんだろうなと痛感します。
さて今日は、「自分がスポーツドクターとしてスポーツ選手のためにできることは何だろう」っていうことに関して考えたことについて書きます。
Contents
スポーツ選手の気持ち
うちの病院は都道県内の多くのスポーツ選手が来院されます。
選手はトップレベルでやっている選手から中高生の選手まで様々です。
中高生の選手も、全国レベルの選手から普通に部活でやっている選手と様々ですが、怪我をして来院される選手はどのレベルでやっている選手であったも、その気持ちは一緒だと思います。
はやくスポーツに復帰したい!
これは、スポーツをやっていて怪我をしたことがある人ならわかるでしょう。
僕も今までに何度も怪我をしているので、怪我をした選手の気持ちは死ぬほどわかります。
 よせやん
よせやん
大学時代に部活のキャプテンとしての最後の試合の前に、膝内側側副靭帯を損傷したときは、ガチガチにテーピングをして鎮痛薬をアップ前と試合前に6錠くらい飲んで試合に出場していました。
医者にいくらやるなと言われようがやっていたでしょう。(今思うとアホですが、その時は本当にそうしていたと思います)
今のシーズンは一般的な中学3年生、高校3年生の多くは引退試合を控えています。
そういう選手が怪我をした場合も程度の差はあれ、そのときの自分と同じような気持ちを抱く選手がほとんどだと思います。
そんな選手を診察した場合、僕たちにスポーツドクターとしてできることは何なんだろうかと最近よく考えることがあります。
 よせやん
よせやん
スポーツ選手のためにできること
再発予防
大前提として、スポーツ選手にとって最適な治療を選択する必要があります。
最適な治療は、その選手のバックグラウンドや試合日程などによって変わる可能性があります。
そして、病院で怪我をした選手を見ていく場合、復帰して再発することがないように必要充分な時間をとって、段階的にスポーツに復帰していってもらいます。
足関節骨折の場合を例にしてみると、術後、まず可動域訓練からリハビリを開始してもらい、1/3荷重、1/2荷重、2/3荷重、全荷重などと徐々に体重をかける量を増やしていってもらいます。
そして、レントゲンやCT写真で骨癒合していることが確認できたら、ジョギングから開始してもらい、徐々に負荷を上げて、その2週間後くらいに完全復帰できるように調整していってもらいます。
また、復帰した後に同じような怪我を受傷しにくくするために、怪我をした原因(体のタイトネスやアライメント不良、筋力不足など)を探し、それを改善するためのトレーニングを指導していくことも重要ですね。
長い目で見たとき、この再発予防は極めて重要になってきます。
スポーツドクターとしては、そこまで介入する必要があると僕は思います。
 よせやん
よせやん
最近はどの医学の分野でも予防医学の重要性が指摘されています。
スポーツ医学においてももちろんそれは同様です。
啓発・指導
しかし、スポーツ選手は実際に怪我をするまで予防に関して関心を持てる選手は少ないように思います。
こういう部分も、怪我で苦しむスポーツ選手を少なくするために、スポーツドクターとして啓発・指導する活動ができたら素晴らしいですよね。
今はとてもそんなえらそうことを言えるような立場ではありませんが、自分が直接絡む選手には指導できるように勉強は今後もしっかりとしていきたいと思います。
少しでもいい状態でプレーをさせる
ただ、スポーツ選手には冒頭で述べたように多少の無理をしてでもやらなきゃいけないときもあるかと思います。
そんなときでも、実際には医療者として、プレーすることの危険性を伝え、きちんと治療に専念してもらうように説得すべきです。
将来のことを考えたら絶対にそうすべきです。
しかし、それでも無理をしてプレーしてしまう選手は必ずいるでしょう。
そんなときに、魔法のように怪我を治してあげることはできないですが、説得した上で選手がどうしてもプレーすると言うのであれば、少しでもいい環境でプレーできるように協力してあげることも時には必要なのかなと思います。
できることとしては、早期復帰を最優先にした治療を行う、テーピングやプレー後のRICE療法の指導する、鎮痛薬を処方することなどでしょうか。
一整形外科医としては、選手が怪我を確実に治して再発しないように安全に診療していくべきですが、スポーツドクターとしてはそれだけでなく、その選手の状況を踏まえた上で最良の治療を提供してあげるべきなのかなと思います。
本当に危ない状態・疾患を見逃さない
ただし、例えば試合中の脳震盪など、選手がいくらやりたいと言っても絶対に無理をさせてはいけない状況はあります。
それを把握するためにも、まず疾患一つ一つの治療をきちんと理解しておくこと、そして、多少無理させていい状況と絶対に無理をさせてはいけない状況の境界線を理解しておくことが大切です。
絶対に無理をさせてはいけにあ状況であれば、選手に何とかして納得して治療に専念してもらうこともスポーツドクターの努めでしょう。
そして、多少の無理が可能な状況ならば、ときにはリスクをきちんと説明した上で攻めの医療を提供することも必要なのかもしれませんね。
おわりに
以上、今回は自分がスポーツドクターとしてスポーツ選手のためにできることは何だろうっていうことに関して考えたことを書きてみました。
怪我をしたスポーツ選手を診察するとき、大事な大会や試合に間に合わせることを目標に治療していくことは多いかと思います。
例えば、筋挫傷を受傷した選手が少し時間が経過してから来院されて、プンクでも血腫が抜けない状況のときに、1週間後の引退試合に何とか出場させてあげるためにエコー下で5mm程度の傷一つでシェーバーによる血腫除去をしたりなど工夫すれば選手のスポーツ復帰を何とか早めてあげることができることもあります。
そして、大会のあとに選手が外来にやってきて、先生のおかげで試合に出ることができましたって言葉を聞くと、本当にこの仕事をしていてよかったなと思えます。
まさにこういうことがしたくて医者になったのですから。
これからも怪我で困っているスポーツ選手を少しでも支えられるスポーツドクターになりたいと思います。
そのためには勉強しなければいけないことは本当にたくさんあります。病院での仕事はきっちりこなしながら、時間を作ってしっかりとやっていきたいと思います。
あとは可能な限り自分もアスリートであり続けたい。
体も心もすごい疲れちゃうときはありますが、スポーツ選手の心を理解する上でも自分もスポーツはある程度しっかりとやれるレベルで続けていきたいと思います。
本気でスポーツ医学と運動器診療を学びたい人のために!
- どこにいても(都会でも地方でも)
- 誰でも(医師・理学療法士・鍼灸師・柔道整復師・トレーナー・学生などスポーツに関わる全ての人)
- いつでも(24時間)
利用可能なスポーツセミナー動画配信サービス!!
1週間1円トライアル実施中!!