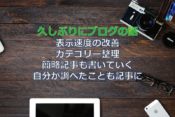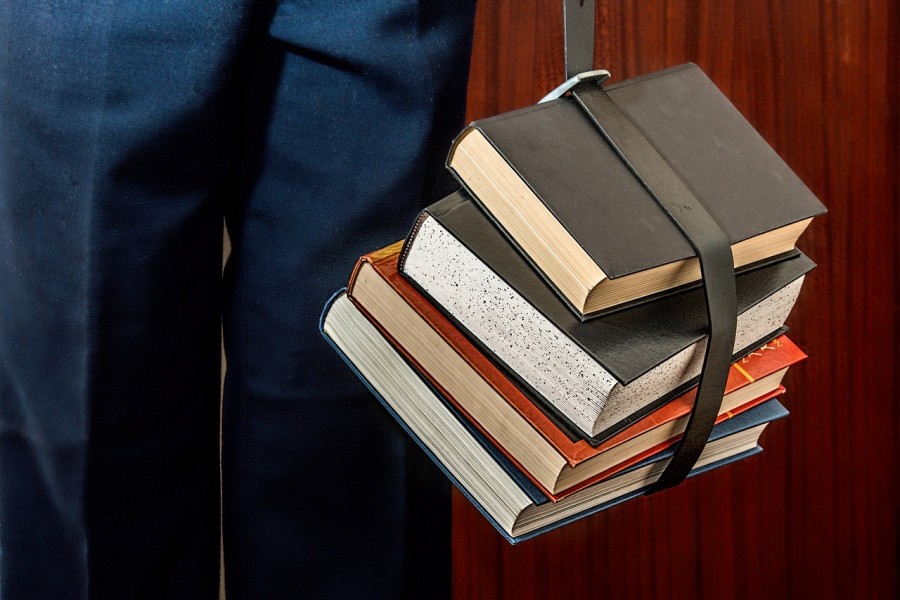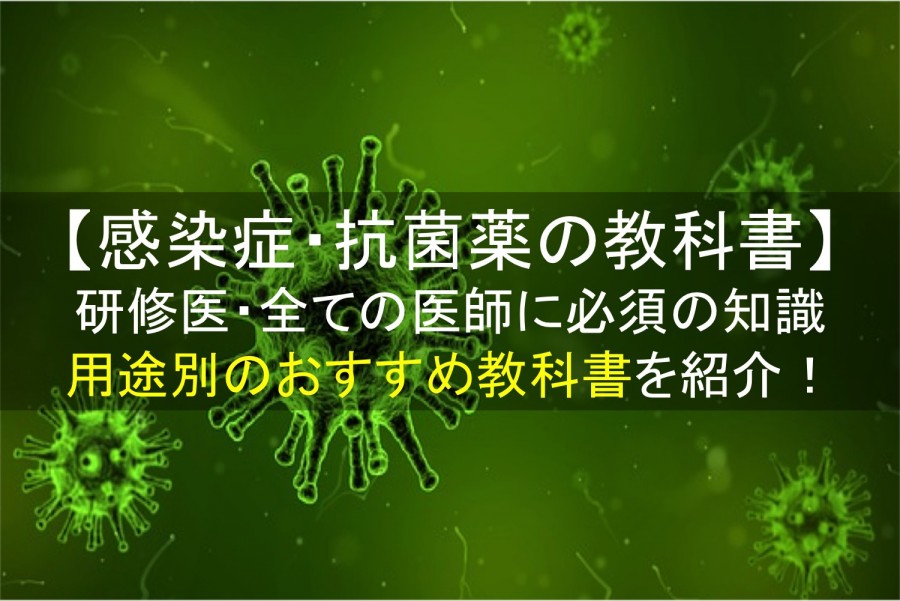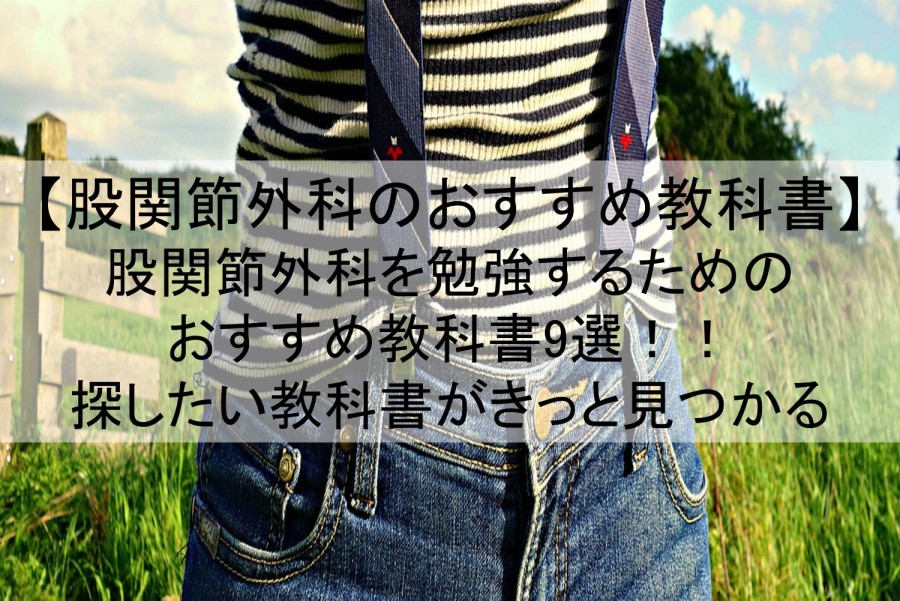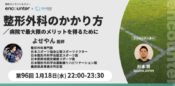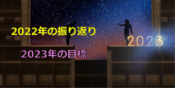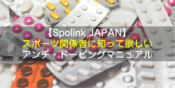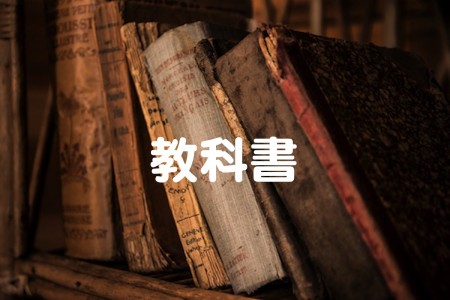長引く膝の痛み、腰痛に対するとても勉強になる教科書を紹介!医療者は常に知識のアップデートを!
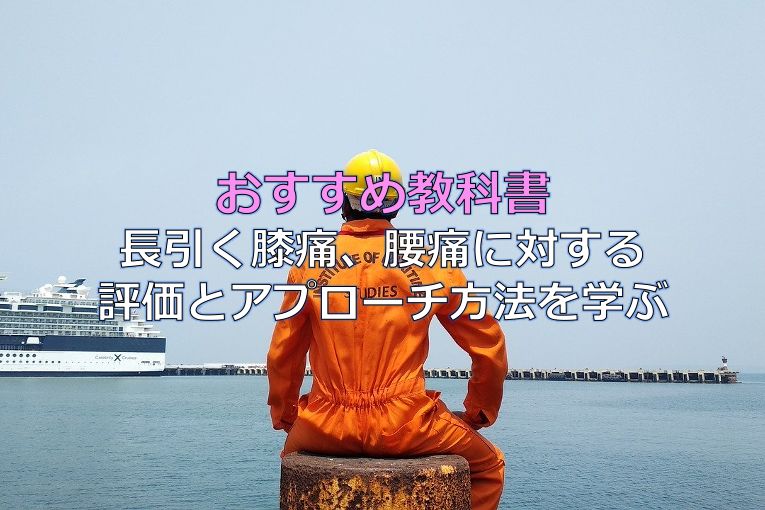
どうも、こんにちは。
整形外科医のよせやんです。
 よせやん
よせやん
3月以降、新型コロナウイルスの影響で学会が軒並み中止になっており、定期的な楽しみの学会での教科書物色が最近できていません。
そんな状況下ですが、新しい医学書は着々と出版されています。
というわけで、今日は最近発刊された教科書の中でとても勉強になったおすすめの2冊を紹介します。
今回紹介するのは、長引く膝痛と腰痛に対する評価法、アプローチ方法についての教科書です。
膝痛と腰痛は病院を訪れる患者さんの愁訴の中でも、かなり頻度の高い2つです。
しかし、きちんとした評価をせずに画像で異常がないからといって、なんとなく鎮痛薬を出している医師の方も残念ながらまだまだ少なくないと思います。
自粛を強いられる現在は、今まで曖昧にしていたところをしっかりと勉強し直すいい機会でもありますし、医療者は患者さんのためにも人生勉強であるべきだと思いますので、定期的に知識のアップデートをしていきましょう。
 よせやん
よせやん
Contents
長引く膝の痛みに対する治療戦略
最初に紹介するのは、僕の専門の一つでもある膝についての教科書です。
膝痛に対する治療の原則は、当然のことながら痛みの原因となっている疾患の治療です。
しかし、 膝関節疾患自体の治療を行っても痛みが改善しないことはめずらしくありません。
膝痛で来院された患者さんに一通り検査をして、半月板損傷が見つかり、半月板に対する手術をしたけれども術後も痛みが残っている、とかそういったケースですね。
これは、疾患の病態と痛みの病態が必ずしも一致していないことが一因であると考えられます。
いかに素晴らしい疾患改善作用を有する治療法であっても、痛みが改善しなければ臨床的に有益な治療とはいえません。
原因が明らかである骨折などの外傷では損傷部位を治せば痛みは軽快しますが、変形性膝関節症のような変性疾患では同じような考え方では治療できません。
痛みの原因として半月板損傷、軟骨損傷、滑膜炎、靭帯損傷、筋力低下、アライメント異常などいろいろなものが考えられ、またそれらが複合できに絡み合っている場合もあるからです。
超高齢社会のわが国では,こういった長引く膝痛に対する対策がますます重要となってくるでしょう。
膝関節疾患の診断・治療に関する書籍はたくさんありますが,膝痛自体にフォーカスしたものはあまり目にしません。
この教科書は、長引く膝の痛みに着目し、その発生機序に関する最新の知見をまとめ、新規治療の可能性や将来性まで踏み込んだ内容を知ることができます。
通読すれば痛みを切り口に膝関節疾患を整理することができますし、長引く膝痛の対応で困った時にこの教科書を開けばどこかに治療のヒントが見つかるでしょう。
 よせやん
よせやん
長引く腰痛に対する治療戦略
続いて、上の教科書を見ていたら関連図書で出てきて気になった腰痛の教科書です。
僕は正直今まで腰痛にはあまり興味がありませんでしたが、この教科書も非常に面白く、とても勉強になったので紹介します。
臨床をしていると、CTでもMRIでも異常はないのに、患者さんの症状はすごく強く、投薬しても治らない腰痛って意外に経験すると思います。
こういった腰痛が、いわゆる長らく原因不明とされてきた腰痛なのでしょう。
しかし、近年では画像診断の進歩により、この原因不明とされてきた腰痛の病態が明らかになってきています。
例えば、これまで臀部中央の痛み=坐骨神経痛の部分症状と安直に考えられることは少なくなかったと思いますが、実は上・下臀神経の臀部での絞扼性障害が少なくないと言われています。
このように腰痛の原因が解明されてきた近年では、仙腸関節や仙結節靱帯、上臀皮神経、椎間関節、椎間板は、画像診断では見逃されやすい腰・下肢痛の重要な発痛源であると言われていますが、腰痛の患者さんに対してまだ腰椎レントゲンと腰部の所見しか取っていない整形外科医の方が多いのが実際のところではないでしょうか。
そして、とりあえず鎮痛薬で様子を見ましょうと言われ、原因はよくわからないままいつまでも鎮痛薬を内服している患者さんはめちゃくちゃ多いと思います。
腰痛を主訴に病院を受診する患者さんは整形外科の中でも一番多いと言ってもいい状況にも関わらずです。
この教科書では、今まで原因不明と言われてきた難治性腰痛に対して、仙腸関節や筋膜(fascia)など最新の知見からアプローチする診かた、治し方を解説してくれています。
患者を苦しめる痛みが何に由来するものなのか、そして、その原因に対しどうアプローチすれば痛みを取り除くことができるのかを理解することは、もちろん実臨床において非常に役たちますし、今まで見えていなかった病態が見えて対応できることは非常に面白いです。
原因がわからなかったら仕方がないですが、医学や技術の進歩によって原因が解明され、治療できる疾患についてきちんと知識をアップデートし、臨床に反映させるのは医療者の責務だと思います。
そんな思いも込めて今回紹介しました。
 よせやん
よせやん
おわりに
以上、今回は最近見つけた勉強になる教科書2冊を紹介しました。
自粛を強いられる現在は、今まで曖昧にしていたところをしっかりと勉強し直すいい機会でもあるので、思い当たることがある医療者の方は是非とも参考にしてもらえたらと思います。
整形外科医だけでなく、ペインクリニックなどに勤務されている麻酔科の先生や総合診療科の先生も知っておくといい内容でしょう。
また、最近はエコーの発達により、レントゲン、MRIなどの画像診断を使えない治療院の先生もかなり詳しく評価ができるようになってきました。
適切な評価を行うことができれば、自分で対応できる症例と病院に送った方がいい症例も判断できるようになり、患者さんにとってもより良い環境ができていくと思います。
医療者は人生勉強とはまさにその通りだと思いますので、時折知識のアップデートはしていきましょう。
 よせやん
よせやん
本気でスポーツ医学と運動器診療を学びたい人のために!
- どこにいても(都会でも地方でも)
- 誰でも(医師・理学療法士・鍼灸師・柔道整復師・トレーナー・学生などスポーツに関わる全ての人)
- いつでも(24時間)
利用可能なスポーツセミナー動画配信サービス!!
1週間1円トライアル実施中!!