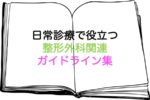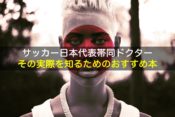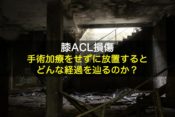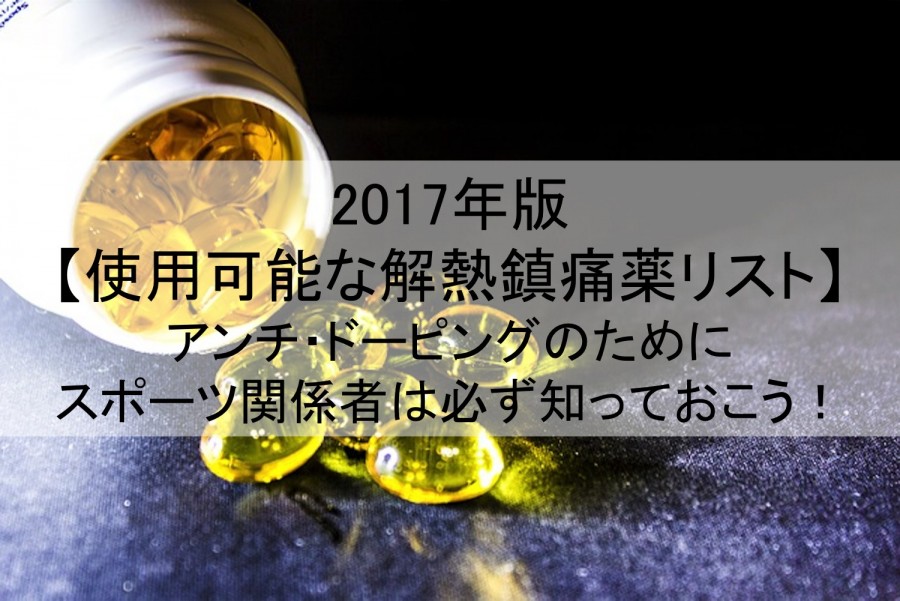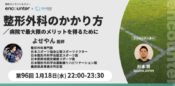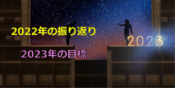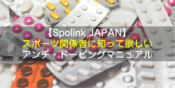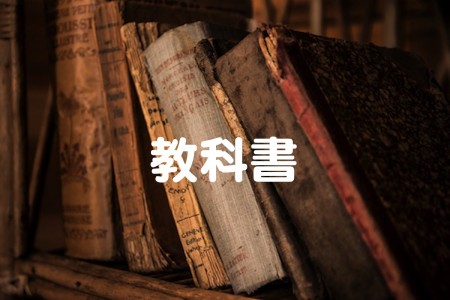膝前十字靭帯(ACL)損傷を発症する危険(リスク)因子とは?

どうも、こんにちは。
若手整形外科医のよせやんです。
 よせやん
よせやん
最近は忙し過ぎて逆にフリーズ気味になってました。
動くことをやめたらダメですね。
というわけで忙しい時こそバシバシ動いていきます!!
今日は、前十字靭帯(ACL)損傷について勉強していきましょう。
メジャーな疾患なので今まで敢えてまとめてきませんでしたが、ここら辺で系統的にまとめておこうかと思います。
ACL損傷は非常に多いスポーツ傷害ですが、手術治療を要することが多く、スポーツ復帰にはかなりの期間が必要です。
ACL損傷のリスクを知っておくことで、積極的に予防トレーニングや動作改善を行うなどの対策が取れる可能性があります。
というわけで、今回は膝前十字靭帯(ACL)損傷の危険(リスク)因子についてまとめていきます。
Contents
ACL損傷の危険因子
ACL損傷の危険因子としては、性別、解剖学的因子、神経筋因子、遺伝的因子、人種、ACL損傷の家族歴などが報告されています。
- 性別
- 解剖学的因子
- 神経筋因子
- 遺伝的因子
- 人種
- ACL損傷の家族歴
これらを順に見ていきましょう。
性別
性別についていくつか文献的なデータを紹介します。
アルペンスキー選手の後ろ向き調査では、女性におけるACL損傷発生率はオッズ比(ACLの危険率)2.3で有意に高かったことが報告されています。
また、フィンランドの9年間の前向き調査では、週4回以上の頻度でスポーツ活動に参加している女性におけるACL損傷の危険率は対照群に比較し8.5倍と男性の約4.0倍より高かったことが報告されています。
これらのエビデンスレベルの高い調査から、女性であることがACL損傷の危険因子と考えられています。
 よせやん
よせやん
では、なぜ女性にACL損傷が多いのでしょうか。
非接触型ACL損傷は月経周期の卵胞期での受傷が多いことが示されています。
これを裏付ける研究として、女性のACL損傷患者は17βエストラジオール、プロゲステロン、テストステロン濃度が対照群と比較して有意に低かったことが報告されています。
また、経口避妊薬使用歴のない症例の相対リスクを1.0とした場合、5年以内に経口避妊薬使用歴のある女性では相対リスクは0.82であったことから、女性ホルモンとACL損傷リスクは関連性があることが示されています。
解剖学的因子
続いて、解剖学的因子です。
脛骨の後方傾斜が大きいこと、顆間窩幅が小さいことがリスク因子と言われています。
近年では、MRIを用いた脛骨関節面の詳細な検討も行われています。
ACL損傷群では対照群と比較して脛骨外側関節面の前後径が有意に小さく、大腿骨・脛骨関節面の曲率半径が小さかったこと、脛骨外側関節面の後方傾斜角4°をカットオフ値とした場合、ACL損傷の予測における感度は76%、特異度は75%であったことなどが報告されています。
また、複数の解剖学的要因からACL損傷リスクを検討した研究もあります。
男性では、ACLボリューム現象(1mm3減少すると危険性が43%増加)と脛骨外側コンパートメントposterior meniscus angleの減少(1°減少すると危険性が23%増加)が危険因子であり、
女性では、大腿骨顆間のアウトレットの狭小(1mm狭くなると危険性が50%増加)と脛骨外側コンパートメントのmiddle cartilige slopeの増大(1°増加すると危険性が32%増加)が危険因子であったことが報告されています。
ちなみに、股関節においては、単純X線像でのcenter-edge angle(CEA)が小さいことが危険因子であることも示されています。
ただし、解剖学的なことを知る機会はないと思うので、なかなか実際の現場における予防には活かせないかもしれませんね。
 よせやん
よせやん
神経筋因子
次に神経筋因子です。
神経筋因子としては、体幹・膝関節の神経筋コントロール不良がACL損傷のリスクとなることが報告されています。
これはACL損傷のメカニズムを考えると、何となく想像つきますよね。
 よせやん
よせやん
その他のものとしては、体幹の側方移動量の増大、ジャンプ着地動作における膝外反モーメントが25Nm以上であること、サイドカット時の筋電図活動電位が半腱様筋腱で低く外側広筋で高いこと、男性の非接触型ACL損傷患者では股関節内旋可動域の低下も有意な危険因子として示されています。
遺伝的因子・人種
最後に、遺伝的因子と人種です。
文献で、コラーゲン遺伝子、血管上皮成長因子(VEGFA)、KDR遺伝子、Matrix metalloproteinases(MMPs)遺伝子における遺伝子型がACL損傷群と対照群との間で異なっていたことが報告されており、ACL損傷に遺伝的要素が関連していることが示されました。
また、両親のいずれかにACL損傷の既往がある場合のオッズ比は1.95であったことから遺伝的要因の関連性が示されています。
ちなみに、WNBA女子バスケットボール選手において行われた研究では、白人選手の受傷率はオッズ比6.55と有意に高く、人種によるACL損傷リスクの違いが示唆される結果でした。
その他
その他のものも紹介しておきます。
米国軍士官候補生を対象にした追跡調査では以下のものがACL損傷のリスク因子として報告されています。
- 全身弛緩性
- BMI
これらは多変量解析で、独立した危険因子であることが示されています。
ACL損傷のリスク因子まとめ
以上のことから、ACL損傷のリスク因子をまとめておきましょう。
- 女性
- 脛骨の後方傾斜が大きい
- 顆間窩幅が小さい
- ACLボリューム現象(男性)
- 脛骨外側コンパートメントposterior meniscus angleの減少(男性)
- 大腿骨顆間のアウトレットの狭小(女性)
- 脛骨外側コンパートメントのmiddle cartilige slopeの増大(女性)
- CEAが小さい
- 体幹・膝関節の神経筋コントロール不良
- 体幹の側方移動量の増大
- ジャンプ着地動作における膝外反モーメントが25Nm以上
- サイドカット時の筋電図活動電位が半腱様筋腱で低く外側広筋で高い
- 股関節内旋可動域の低下(男性)
- 両親のACL損傷既往歴
- 白人
- 全身弛緩性
- BMIが高い
参考図書
2019年に発売されたACL損傷の診療ガイドラインです。
詳しい文献はこちらのガイドラインを参照して下さい。
ガイドラインシリーズは非常に勉強になりますよ。
 よせやん
よせやん
おわりに
以上、今回は膝前十字靭帯(ACL)損傷の危険(リスク)因子についてお話ししました。
これからしばらくACL損傷についてまとめていこうと思います。
また明日以降まとめていきます。
本気でスポーツ医学と運動器診療を学びたい人のために!
- どこにいても(都会でも地方でも)
- 誰でも(医師・理学療法士・鍼灸師・柔道整復師・トレーナー・学生などスポーツに関わる全ての人)
- いつでも(24時間)
利用可能なスポーツセミナー動画配信サービス!!
1週間1円トライアル実施中!!