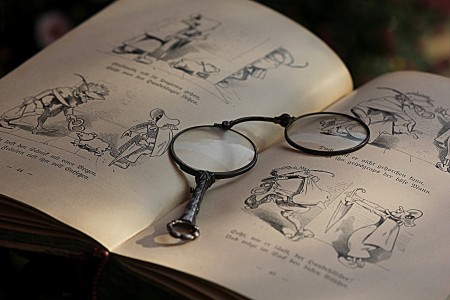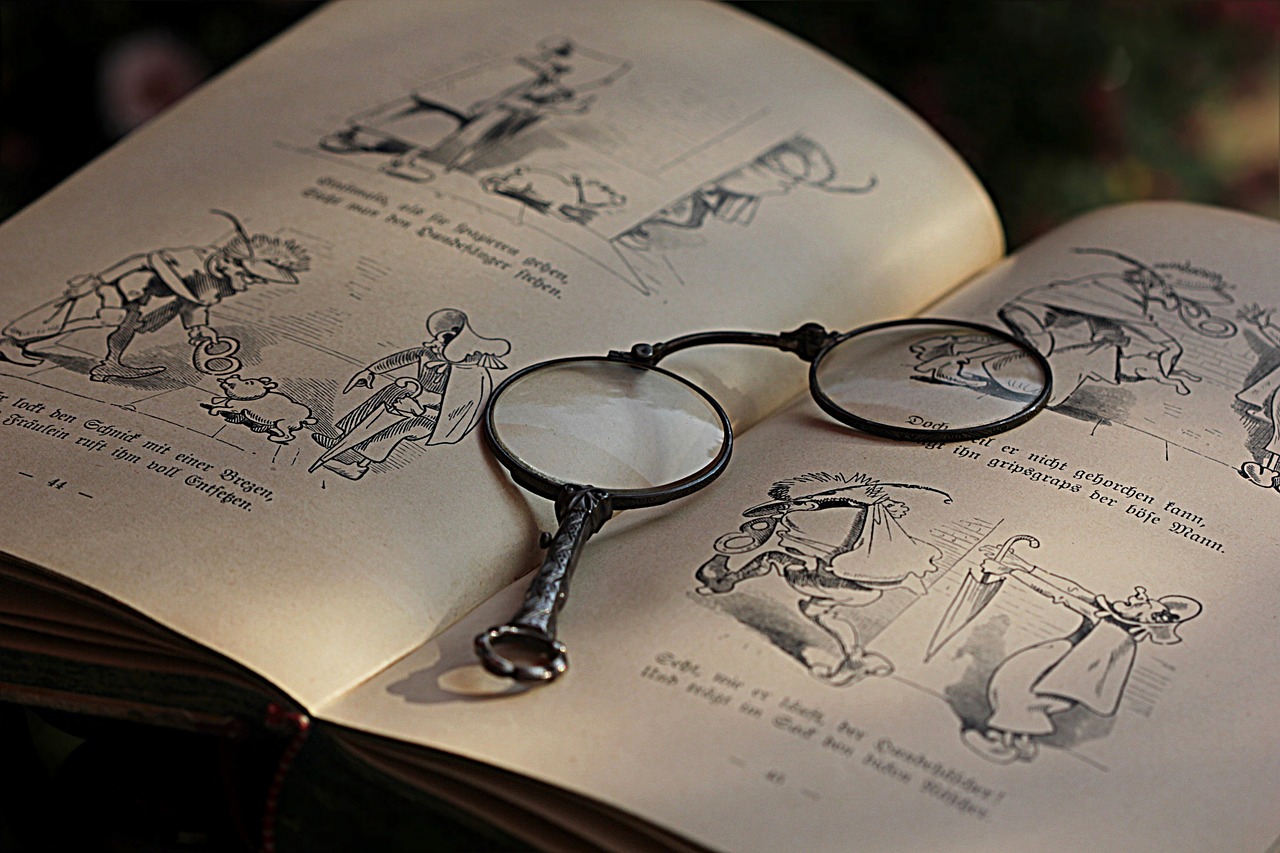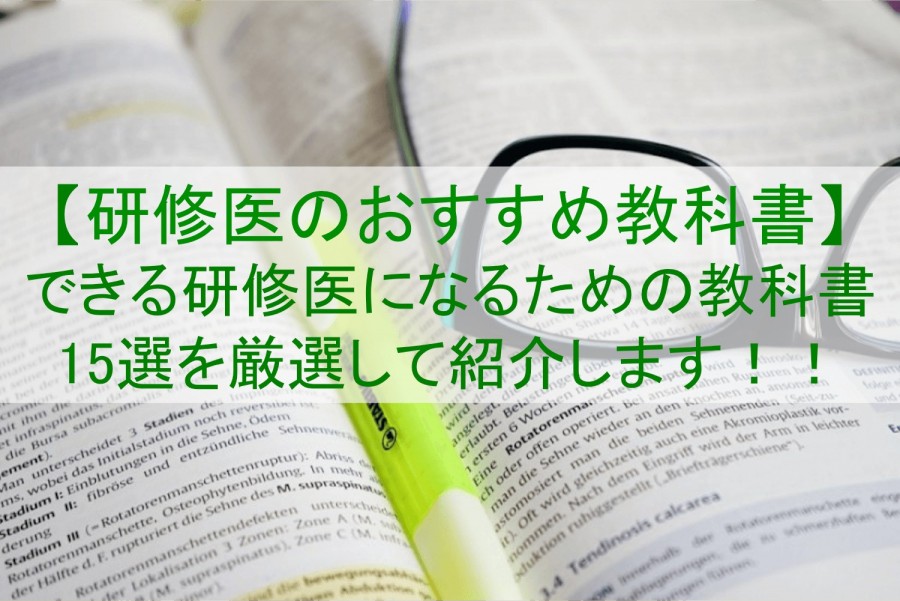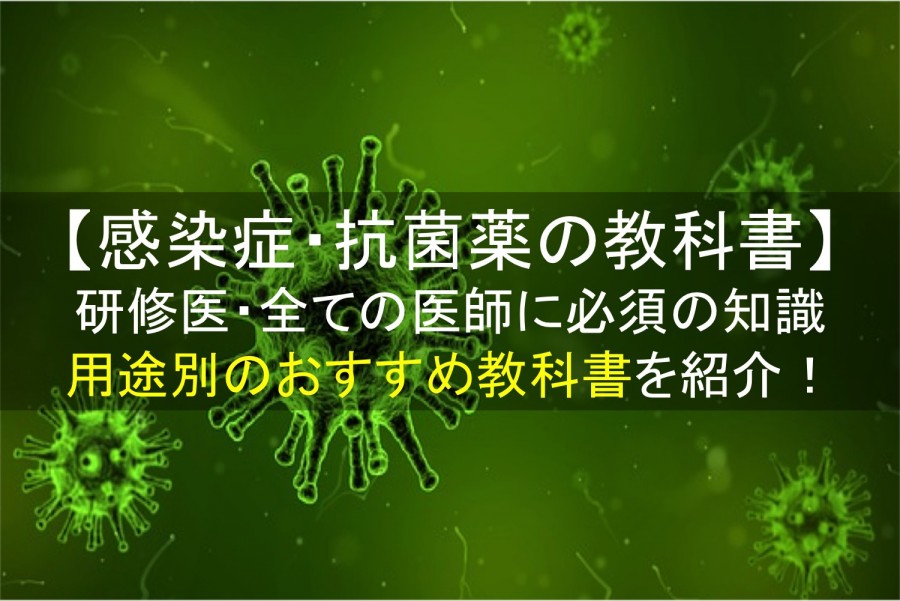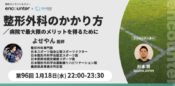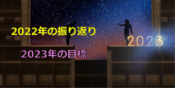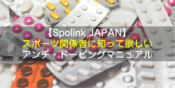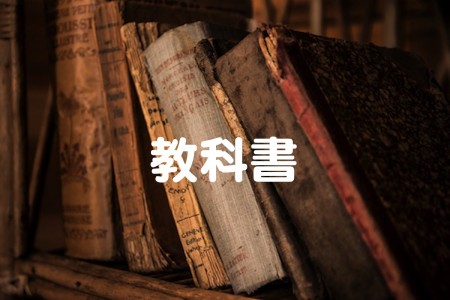整形外科医に必要な内科の知識|最低限の知識は持っておこう!

どうも、こんにちは。
若手整形外科医のよせやんです。
忘年会のシーズンですね。研修医のときは全病棟、ほぼ全部の科の忘年会に呼ばれたので、この時期はほとんど毎日飲んでるような生活でした。整形外科医となった今はそのときほどではないですが、整形外科の忘年会だけでなく、麻酔科やオペ場、小児科、外来などの関係のある部署の忘年会にも呼ばれます。
参加するだけなら全然いいんですが…僕たち若手は何かにつけて芸をやらされます。やってみると意外に面白かったりすることもありますが、正直なところこれがなかなかストレスです。まあ、でもこれは医者だけでなくて社会人みんなに共通でしょうか。
愚痴はこの辺にしておいて、今日は整形外科医になる前に勉強しておくべきことシリーズの最終章をやろうと思います。
今までのこのシリーズの記事を読んでいない方はこちらからどうぞ。
前回は内科的なことの中でも、とくに内科救急(救命処置)についてでした。
今回は、整形外科医に必要な内科的な知識についてまとめます。
Contents
整形外科医に必要な内科の知識
整形外科医になって働くようになっても、整形外科の知識だけ持っていたらいい訳ではありません。
たびたび内科的な知識が必要になってきます。
大雑把に言うと、以下の2つです。
- 周術期管理
- 内科的合併症の治療
では、これらについて具体的にみていきましょう。
周術期管理
まず、周術期管理です。
整形外科は外科系の科ですから当然のことながら手術が基本です。手術を行う場合、患者さんの周術期管理をしていく必要があります。これが意外に覚えなくてはいけないことが多く、内科的な知識も必要になってきます。
周術期管理は大きく分けると、以下の3つに分けられます。
- 術前管理
- 術中管理
- 術後管理
ではこれらについて、さらに具体的にどういうものがあるのでしょうか。
術前管理
まず、術前管理です。
術前管理は非常に重要であり、この管理ができていないと手術そのものができなくなる可能性もあります。
- プレメディケーション
- 絶飲食の時間
- 糖尿病コントロール
- ステロイドカバー
まずは、プレメディケーションですね。術前および術当日に薬を止めるか、内服するかを考える必要があります。
わかりやすいのは、術中の過度の出血を予防するために、抗凝固薬(血液をさらさらにする薬)を止めるなどといったことです。抗凝固薬に関しては、この薬なら手術何日前に止める、といった内容を覚えておく必要があります。
次に絶飲食の時間ですね。
これは、全身麻酔なのか脊椎麻酔なのか伝達麻酔なのかでも変わってくるでしょう。また、絶食させるかどうかによって、先ほどのプレメディケーションとして糖尿病薬を止めるかどうかも判断しなくてはいけません。
そして、糖尿病患者さんの場合には、血糖値のコントロールを行う必要があります。
怪我をして術前検査を受けて初めて糖尿病に気付くケースは意外と多いですし、糖尿病として治療されてはいるもののコントロール不良の場合があります。また、周術期は特にスライディングスケールに関する知識も持っておく必要があるでしょう。
最後に、ステロイドを長期間内服している患者さんの場合には、ステロイドカバーをする必要があるかもしれません。これもステロイドをどれくらいの量、どれくらいの期間内服しているとステロイドカバーが必要になるのかなど知っておく必要があります。
術中管理
続いて、術中管理についてです。
安全に手術を終えるため、手術をしやすくするため、不測の事態が最悪の事態にならないように術中管理についてもしっかりと勉強しておく必要があります。
- vitalコントロール
- 救命処置
まず、vitalコントロールです。
麻酔や手術によりvitalは刻一刻と変化します。麻酔後や手術中にvitalが変動した場合に、それに応じた対応をする必要があります。例えば、血圧も脈拍も落ちてきたのであればエピネフリンを使う、徐脈になってきたらアトロピンを使うなどですね。また、後述しますが輸液のコントロールも重要になってきます。
そして、これに関連して、万が一の場合のために救命処置の知識も必要になります。
実際に大量出血によりショックになったり、抗生剤や麻酔薬にあるアレルギー性ショック、喘息の急性増悪により気道閉塞しショックになることなどは手術室でリアルに起こりうることです。これら不測の事態が起きたときに、しっかりと処置をして術中死という最悪の事態は防がなくてはなりません。
術後管理
最後に術後管理です。
- 輸液・輸血
- 疼痛コントロール
- 抗生剤の投与
まず、輸液・輸血です。
術中もそうですが、術後は術中の出血量や術後尿量などを考慮して輸液の量を調整する必要があるでしょう。また、vitalや尿量を確認して、その後も輸液量を調整していく必要があります。
術後に貧血が進んできた場合には、輸血が必要になることがありますが、どれくらいなら輸血を行うか、どれくらいの量を輸血したらHbがどれくらい上がるか、どんな輸血を行うかなどを判断する知識が必要です。
そして、術後には疼痛管理も重要になってきます。
当然のことながら、手術後は個人差はありますが基本的に患者さんは痛いです。この痛みをコントロールしてあげることは非常に大切だと思います。内服薬を使うのか、坐薬を使うのか、点滴を使うのか、その患者さんの既往や体格、年齢によって調整してあげる必要があるでしょう。また、伝達麻酔を行うことも疼痛管理においてはよい手段となります。
あとは、抗生剤の投与のタイミングです。
ターニケットをまく前に最初の抗生剤を行くと思いますが、次の抗生剤をいつ行くかなど明確なプロトコルを持って決めていますか?ここに関しても、勉強しておくとよいでしょう。

内科的合併症の治療
そして、整形外科医として意外に多く経験するのは内科的合併症の治療です。
感染症
特に多いのは肺炎や尿路感染症などの感染症でしょう。
研修医時代に整形外科を回ったときに、外傷で入院してくる高齢の患者さんの感染症に罹患する割合が想像していた以上に高くて驚きました。
高齢者は加齢により膀胱の排尿機能が低下しやすいため、尿路感染症を起こしやすいとされていますが、特に下肢の外傷でベッド上にいる時間が長かったり、おむつを使用していると当然、上行性感染のリスクは高くなります。
また、加齢により嚥下機能が低下しやすいのに加え、脊椎外傷の患者さんでギャッジアップ(ベッドで上半身を起こすこと)ができない場合は、食べ物や飲み物を誤嚥し誤嚥性肺炎になるリスクは当然高くなるでしょう。
これらも嫌ですが、創部感染症はもっと困ります。こちらに関する診断・治療法も理解しておく必要があります。
深部静脈血栓症
整形外科の術後に多いものとしては、あとは深部静脈血栓症などでしょうか。
深部静脈血栓症は、特に下肢の術後の患者さんの多くに見られます。ほとんどは遠位型ですが、近位型の場合には肺塞栓症などの危篤な疾患を引き起こす可能性があるため、専門家にコンサルトする必要があります。遠位型の場合は、自科で加療することが多いのではないでしょうか。
どの静脈から近位を近位型というのか、自家で治療を行う場合にどうやって治療すればいいのか知っておかねばなりません。
まとめ
以上、今回は整形外科医に必要な内科的な知識についてまとめました。
自分は整形外科医だから内科的なことは何もしなくてもいい、とはなりません。入院患者さんが糖尿病だからといって、毎回内科に周術期の血糖コントロールを依頼したり、患者さんが肺炎になったからといって、全例内科にコンサルトすることはできないでしょう。
そもそも、そんな格好の悪い整形外科医にはなりたくありません。もちろん、重症の場合や、自分で治療して上手く行かない場合は必ず、専門家にコンサルトするべきだと思いますが、基本的な治療はできるようになっておきましょう。
今回出てきた項目については、また別個にまとめていくつもりです。
本気でスポーツ医学と運動器診療を学びたい人のために!
- どこにいても(都会でも地方でも)
- 誰でも(医師・理学療法士・鍼灸師・柔道整復師・トレーナー・学生などスポーツに関わる全ての人)
- いつでも(24時間)
利用可能なスポーツセミナー動画配信サービス!!
1週間1円トライアル実施中!!