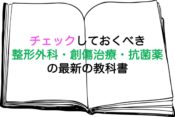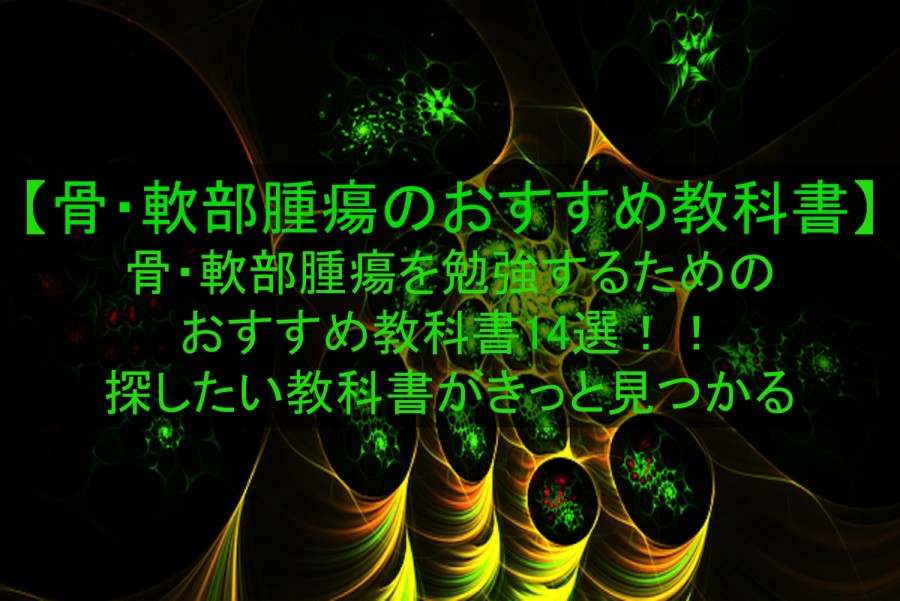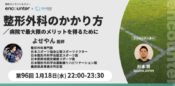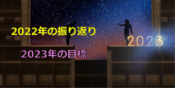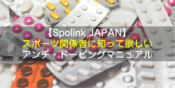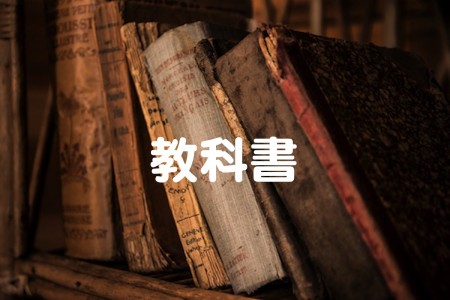足の外科を勉強するためのおすすめ教科書|用途別にマニアックに紹介

どうも、こんにちは。
若手整形外科医のよせやんです。
 よせやん
よせやん
このブログを始めて1週間半ほど経ちました。
まだまだブログに関しても勉強しながら試行錯誤しているので、日々ブログの見た目が変わっています。
よかったらどこが変わっているか探してみてくださいね。
意外にそんな細かな変化を感じてみるのも楽しいかもしれません。
今日やっと本などを紹介できるようにブログが進化したので、さっそく第1回を書いていこうと思います。
まず、僕が興味のある分野である足の外科のおすすめ教科書を紹介します。
足の外科は近年、急速に発展してきた分野であり、足の外科の疾患に関する知識や診察方法などはまだ十分に周知されていない部分もあります。
また、足の外科は非常に難しく、多くの知識を必要としますが、なかなか勉強する機会はないと思います。
僕は上司に足の外科を専門にしている先生が数名いらっしゃるので、足の外科の疾患の診療や手術に立ち会う機会が多いですが、足の外科に関してはあまり知らない、足関節鏡なんて見たことがないという先生もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、そんな足の外科を勉強するためのおすすめ教科書を用途別に紹介していきたいと思います。
 よせやん
よせやん
Contents
足の外科の総論
まず、足の外科の総論を学ぶための教科書を紹介します。
最初に紹介するのはこの教科書です。
この教科書は、足の外科のバイブル的な教科書です。
足の外科のメッカである奈良県立医科大学および関連病院が所有する豊富な足の疾患・外傷所見で構成された成書であり、日本整形外科学会の専門医試験の参考図書のひとつに加えられています。
「扁平足」や「外反母趾」、「足関節鏡」など昨今の治療発展がめざましい項目を中心に最新の知見を揃え、足部の各種疾患・外傷およびその治療についてカラー写真とイラストで見やすく、わかりやすく提示してくれています。
こちらの教科書は、足の外科を勉強するために最初に揃えるべき教科書と言えるでしょう。
足の外科全般を学ぶ教科書として、もう一冊紹介しておきます。
これは、日本足の外科学会教育研修委員会が作成してきたテキストと日本整形外科学会研修指導マニュアルに含まれる足の外科領域のトピックスをまとめて作られた教科書です。
2018年に発刊された教科書ですが、非常によくまとまっており、上述した足の臨床とは少し趣が異なります。
若手整形外科医にとっては足の外科の日常診療をレベルアップさせる絶好の教科書であり、「エキスパートオピニオン」などの発展的な内容により足の外科を専門としている先生にとっても治療の参考になるように作られています。
足の外科の勉強はまずこれらの教科書を使い、さらに毎年足の外科学会が主催で開催している足の外科研修会で最新の知見をupdateしていくのが一番いい勉強法かと今は思っています。
 よせやん
よせやん
足の外科の一般的な手術
次に、足の外科領域の手術の教科書です。
まず、OS NOW、OS NEXUSシリーズをまとめて紹介します。
このシリーズはやはり優秀で、実際に手術する立場で読んでも非常にポイントがまとまっていて使いやすいです。
手術手技の基本的な流れの解説はもちろん「手術のコツと注意点」「トラブルシューティング」が随所に掲載されており、術中トラブルや合併症への対処法なども解説されています。
また、OS NEXUSには電子版が付いているので、手軽に繰り返し読めるのも大きなメリットです。
もう1冊紹介しておきます。
こちらは、足の外科の人なら知らぬ人はいない高尾先生の書かれた教科書です。
一般的な手術書では学ぶことができない「治療戦略」&「手技」の秘策や盲点を「Point」形式で余すところなく解説してくれています。
同疾患治療に特化した重城病院CARIFAS足の外科センターの症例をベースに、診療から手術、後療法までの一連の流れを400枚以上の写真とイラストで細部まで分かりやすく解説し、臨場感あふれる構成となっています。
どちらかというと、足の外科を専門としている方向けの教科書になるかと思います。
 よせやん
よせやん
外反母趾の手術
外反母趾は非常に多い変性疾患であり、足の外科を専攻していると必ず見ることになる疾患です。
外反母趾の教科書はこれ1冊を持っていれば全て理解できると思います。外反母趾の基礎的な知識や解剖を始め、もちろん手術まで学ぶことができます。
手術だけならばSurgical Techniqueもかなりオススメです。
手術の細かい手順やピットフォールについては、こちらの教科書の方がより詳細に学べるとは思います。
足の外科の外傷
続いて、足の外科の外傷の教科書です。
外傷ならやはりSurgical Techniqueが有用です。
特に、ピロン骨折は足の外科専門医に手術が回ってくることも多々あります。
大変な症例はかなり大変なので、足の外科を専攻するならばしっかりと勉強しておきたいところです。
足関節鏡手術
続いて、足関節鏡手術を学ぶための教科書を2冊紹介します。
足の鏡視所見は膝と違って真っ白な世界であり、予習してないとまったくわからないという事態に陥る可能性があります。
足関節鏡における各手術部位でのポータルの作成位置や実際の鏡視所見などを教科書で確認しておくとよいでしょう。
1冊目はこちらの教科書です。
僕は、足の関節鏡手術に関して勉強するときはこの教科書を使っています。
奈良医大の田中先生が編集された教科書であり、実際の手術の際の細かい注意点が、著明な先生方の分筆で書かれていて、非常に参考になります
さらに、解剖の写真や、最近流行りのエコーにも言及されています。
足関節鏡を学びたいという方には、ぜひともおすすめの1冊です。
 よせやん
よせやん
ただし、専門書として使っていると、少し足りない部分もあり、僕は上の高尾先生の教科書を併用するようになりました。
もう1冊の足関節鏡手術の教科書がこちらです。
こちらは日本足の外科学会教育研修委員会機能解剖セミナー班の先生方が執筆され、帝京大学の高尾先生が編集された教科書です。
この教科書は、正確な術前診断に基づき、イラストレイテッドにフローチャート形式で関節鏡の正しい手技が習得できる足関節内視鏡手術の指南書であると言えるでしょう。
この2冊はどちらも足関節鏡手術を基礎から学ぶための非常にいい教科書なので、どちらかは持っておくとよいでしょう。
 よせやん
よせやん
創外固定
続いて、足の外科を専門としていくなら知っておきたい創外固定の教科書です。
創外固定は軟部組織を損傷しない低侵襲な固定であり、骨折の治療だけでなく、変形矯正や骨延長など広い適応があります。特に、リング型創外固定器は原理や使い方を勉強していないと、手術を見ていても全く意味がわからないと思います。
まず紹介したいのはこの教科書です。
僕はこの教科書を使用しています。
イリザロフとTaylor spatial frameについては主にこれで勉強しました。
骨折治療だけでなく、創外固定の色々な使い方が載っていますし、創外固定の基礎から応用まで幅広く学ぶことができます。
 よせやん
よせやん
もう一冊、OS NOWも紹介しておきます。
OS NOWシリーズを集めている方はこちらでもいいかもしれません。
かなりマニアックになりますが、Taylor Spatial Frameだけを勉強するならそれ専用の教科書があります。
Taylor Spatial Frameは矯正などでも非常に有用ですが、使い方がわかっていないとなかなか手を出せません。
勤めている病院でTaylor Spatial Frameを使っている場合はこちらもいいと思います。
足の画像診断
そして、足の画像診断の教科書です。
足の撮影には、その疾患ごとに最適な撮影方法があります。
放射線科医のいない施設でも、十分なクオリティで撮影できるように撮影方法に関しても解説されています。
この本の大きな特徴は足の外科の疾患ごとに特徴的な観察すべき構造物の走行をふまえて、それらが最もよく見える画像が掲載されていることです。
意外と足のMRI画像ってちゃんと見たことがない、勉強したことがないという方も多いのではないでしょうか。
足の外科学会のときに購入したのですが、もっと早く使っていればよかったと後悔しています。
この本は非常にいい本であり、足関節の画像診断をきちんと学びたい方にはぜひともおすすめしたい1冊です。
 よせやん
よせやん
インソール(足底板)
次にインソール(足底板)の教科書です。
足の外科をやっていると、インソールを治療に使うことはめちゃくちゃ多いです。足の外科の疾患のまず最初にやる保存療法といっても過言ではありません。
インソールの教科書は正直あまりないのですが・・・
こちらの教科書はインソールを作成するための技術的なものではありますが、インソールの定義や種類、役割、効果、問題点などの総論を学ぶことができます。
少なくとも、どういう疾患にどのようなインソールを用いるのか知っておくといいかと思います。
 よせやん
よせやん
足の外科を気軽に勉強した方向け
あと、いわゆるお堅い教科書ではなく、足の外科について気軽に勉強したいという方におすすめの教科書を紹介しておきます。
足の外科の治療においては前述の通り、「靴」と「インソール」が欠かせません。この教科書では、どう考えて靴を選び、どのようにインソールを作るか、医者だけでなく、看護師、装具士、シューフィッター、さらに患者さんにも役立つように書かれています。
日常診療での理解に役立つよう浅く広く足部疾患が紹介されており、足診療に対する考え方やちょっとポイントや散りばめてあって、飽きなく読み切ることができます。
 よせやん
よせやん
上と同じシリーズの教科書で、こちらは手術手技について書かれています。
こちらも、著者の臨床家としての豊富な体験を踏まえた上での愚痴や皮肉が非常に楽しく飽きなく読めることでしょう。
最後にこの教科書です。
理学療法士の方向けに書かれた教科書ですが、足と靴にクローズアップした非常に興味深い一冊です。
足と靴は切っても切れないものであり、足の外科を専攻するならば患者さんに合わせた靴の選び方、靴下の選び方、足底挿板の処方、靴の履き方について勉強しておく必要があります。
足部の解剖学的知識、運動学的知識はもちろん、皮膚の状態、アライメントも適切に評価し、それに合わせた靴や靴下、インソールの指導をしなければなりません。
この教科書では写真やイラストで根拠も提示しながら、気軽に学ぶことができます。
 よせやん
よせやん
足の外科の英語の教科書
最後に、足の外科の英語の教科書を紹介しておきます。
医師にとって英語は論文を読んだり、書いたりする上で必ず必要です。
意味の知らない単語や言葉の言い回しを調べる時間を減らすためにも、少しでも慣れておいて損はありません。
これは、世界中で使用されている足の外科領域の解剖の教科書です。
昔からある有名な教科書の第3版で、足の外科における必須の教科書となっています。
足の外科に必要な解剖が驚くほど詳細に書かれています。
足の外科領域のマニアックな解剖と英語を同時にしっかりと勉強したい方におすすめの教科書です。
 よせやん
よせやん
続いて、こちらの教科書は足関節鏡の世界的な教科書です。
21年ぶりの改訂となる第2版が2016年に出版され、近年の足や足首の外科手術における関節鏡の使用に影響を与えている発展についても詳述されています。
足関節鏡と英語をしっかりと勉強したい方におすすめの教科書です。
そして、足の外科の手術に関する英語の教科書がこちらです。
足の外科の手術手技について英語で勉強したい方におすすめの教科書になります。
これが最後に紹介する教科書になります。
これは、上記3つの教科書よりもボリュームが少なくとっつきやすい足の外科全般の英語の教科書になります。
僕はこの教科書を英語の勉強と興味のある足・足関節の勉強をかねて研修医のときに読みました。
1つ1つの内容はそんなに深くなく、割とすぐに読めるので英語があまり得意でない方の導入の教科書としてよいかと思います。
 よせやん
よせやん
さいごに
以上、今回は足の外科のおすすめ教科書を紹介しました。
足の外科は近年、急速に発展してきた分野であり、足の外科の疾患に関する知識や診察方法などはまだ十分に周知されていない部分もあります。
また、足の外科は非常に難しく、多くの知識を必要としますが、なかなか勉強する機会はないと思います。
そういう場合は、まず教科書でしっかりと勉強しましょう。
まあ何はともあれ、日々勉強することのどれだけ多いことか。
勉強してもしても新しく勉強することが湧き出てきます。
前線でやっていくためには、結局医者はいつになっても日々勉強なのかなと思います。
この記事が足の外科の教科書を探している方の参考になれば幸いです。
本気でスポーツ医学と運動器診療を学びたい人のために!
- どこにいても(都会でも地方でも)
- 誰でも(医師・理学療法士・鍼灸師・柔道整復師・トレーナー・学生などスポーツに関わる全ての人)
- いつでも(24時間)
利用可能なスポーツセミナー動画配信サービス!!
1週間1円トライアル実施中!!