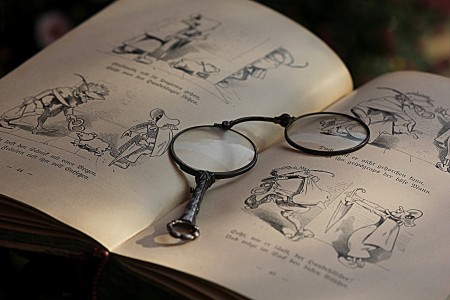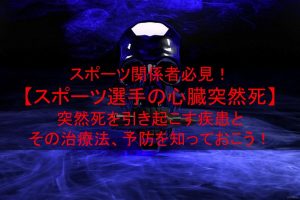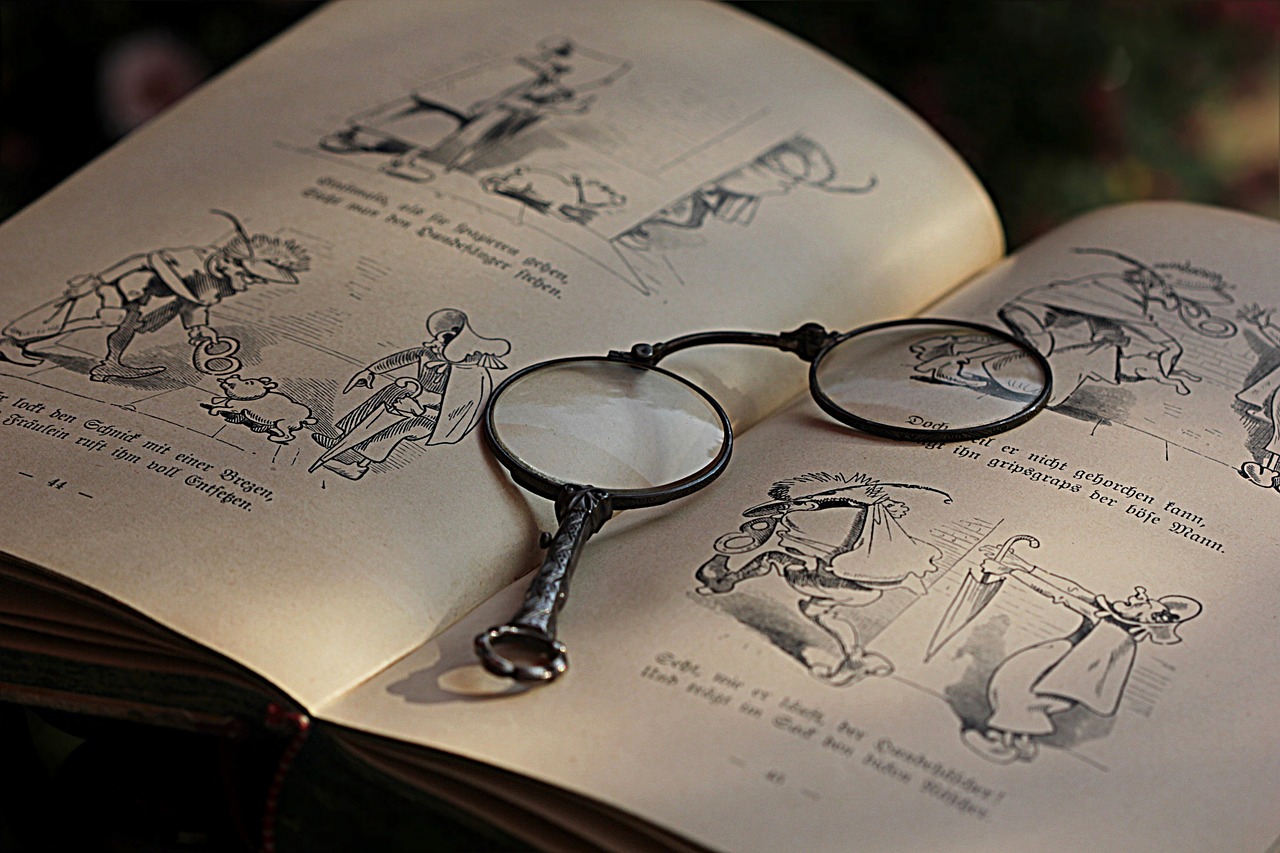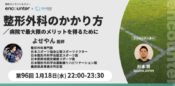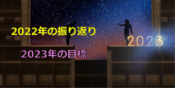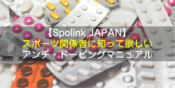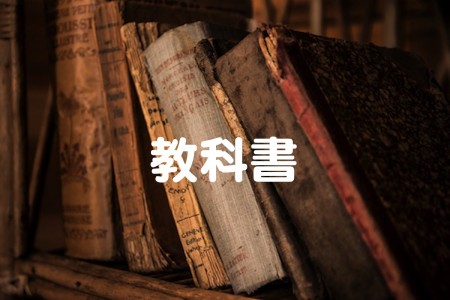内科救急(救命処置)|整形外科医になる前に勉強しておくべきこと

どうも、こんにちは。
若手整形外科医のよせやんです。
今日は都道府県リーグの入れ替え戦がありました。ずっと攻勢でしたが点を決めるきることができずにPK戦。そして負けてしまいました。というわけで、今まさに意気消沈中です…。
さて、今日は整形外科になる前に勉強しておくことシリーズです。
今までの記事は下からcheck。
今回は内科救急(救命処置)に関して書いていきます。
Contents
内科救急(救命処置)
前回の記事で救急外傷の診察・治療は大事ですよって話をしました。
ただ、それだけではなく、内科救急の知識も非常に大切になってきます。
整形外科医になったら、当然外傷を多くみることになるでしょう。若年者ももちろんいるでしょうが、患者の多くは高齢者です。90歳超えの患者も今やめずらしくありません。骨折の背景に骨粗鬆症がある可能性を考えたら当然ですね。

そして、90歳を超える患者を複数人担当していると、必ず一人は肺炎や尿路感染症、脳梗塞などの内科的合併症を併発します。
それを治療して回復してくれたらいいのですが、心肺停止(cardiopulmonary arrest:CPA)になってしまう方が出てきます。こうなると、当然心肺蘇生(cardio-pulmonary resuscitation:CPR)およびその知識が必要になります。
また、手術中に患者が徐脈になったり、血圧が上昇・低下することもあるでしょう。それだけではなく、場合によって麻酔の影響でアレルギー性のショックが起こることもあり得ます。
そして、スポーツドクターとして、何かスポーツイベントに参加しているときに、競技者がCPAになることがあるかもしれません。特にマラソンなどでは毎年、そういった報告が散見されますし、サッカー・フットサル・野球などでも心臓疾患や心臓震盪による競技中のCPAが怒ることがあります。
というわけで、整形外科医であっても内科救急の知識は絶対に持っておいた方がよいです。特に、研修医の間は内科当直もするわけですから、必ず研修医の間に勉強しておくべきです。
内科救急(救命処置)の資格
では、どうやって勉強するか。
日本には下記の3つの講習会があります。
- BLS(Basic Life Support)
外部リンク:BLS公式ホームページ - ACLS(Advanced Cardiovascular Life Support)
外部リンク:ALCS公式ホームページ - ICLS(Immediate Cardiac Life Support)
外部リンク:ICLS公式ホームページ
BLS、ACLSはアメリカ心臓学会(American Heart Association:AHA)がアメリカの蘇生ガイドラインの内容に則して作成した講習会です。
BLSでは一次救急処置、つまり、基本的なCPRとAEDの使い方などを勉強できます。
ACLSでは二次救急処置、つまり、病院など設備の整った環境で行われる気管内挿管や薬剤投与などを勉強できます。
ACLSを受講するためには、BLSを受講済みである必要があります。
ICLSは日本救急医学会が日本の蘇生ガイドラインの内容に則して作成した講習会で、成人の心停止に対する対応(一次救急処置・二次救急処置)を勉強することができます。

アメリカのガイドランでも、日本のガイドラインでも基本的に内容は変わりません。
ごくわずかに異なるところもありますが、内科救急の知識が学べれば別にどちらでもいいと思います。
ただ、ACLSとICLSのどこが違うのかだけ明記しておきます。
ACLSは成人の心停止だけではなく、徐脈や頻脈といった不整脈・急性冠症候群・脳卒中・自己心拍再開(Return of Spontaneous Circulation:ROSC)後のケアなどのCPAになる前や、ROSC後の対応まで学ぶことができます。
対して、ICLSは成人の心停止に対する救急処置(BLS+ACLSの初歩という感じです)を学ぶことになります。
今後のことを考えても、僕はACLSを受講しておくのがいいかと思います。
僕も研修医1年目の夏までにBLS、ACLSを受講しました。
その他の救急の資格
その他、研修医の間に取っておいた方がいいと思う資格に
・PALS(Pediatric Advanced Life Support)
外部リンク:PALS公式ホームページ
・ISLS(Immediate Stroke Life Support)
外部リンク:ISLS公式ホームページ
があります。
PALSはBLS・ACLSと同じくAHAによる講習会で、小児の緊急事態に対する二次救命処置を勉強することができます。
PALSを受講するためには、BLSの受講を終えている必要があります。
ISLSは脳卒中の可能性のある患者に対する、蘇生の理想的な基礎診療のコンセプトを勉強することができます。
実際の脳神経外科の治療に関してではなく、患者を評価するところまでです。
こちらを受講するためにはBLS・ACLS・ISLSなどの救命処置コースの受講を終えている必要があります。
特にGCS(Glasgow Coma Scale)の評価方法はすごく勉強になりました。
脳震盪疑いの患者と出会ったら、GCSを評価する必要がありましたね。
GCSの評価、自信を持ってできますか?!
おわりに
長くなってきたのでここら辺で終わっておきましょう。
救急の項目で終わってしまいました。
次回、最後に一般内科の話をしようと思います。
本気でスポーツ医学と運動器診療を学びたい人のために!
- どこにいても(都会でも地方でも)
- 誰でも(医師・理学療法士・鍼灸師・柔道整復師・トレーナー・学生などスポーツに関わる全ての人)
- いつでも(24時間)
利用可能なスポーツセミナー動画配信サービス!!
1週間1円トライアル実施中!!